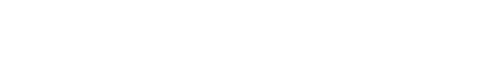2025/04/18
はじめての障害者雇用でも安心!履歴書の基本・自己PR・配慮事項の書き方ガイド

スタッフ
こんにちは!障がい者のための在宅就労求人.comです。
今日は履歴書の基本について徹底解説をしていきたいと思います。
目次
- 履歴書を書く際に気をつけるべきルール
- 基本情報の書き方
- 学歴・職歴の書き方|正しく・丁寧に伝える履歴書作成のコツ
- 免許・資格の書き方|履歴書で強みをしっかり伝えるコツ
- 志望動機・自己PRの書き方|自分らしさを言葉にしよう
- 障害についての書き方|“伝えることで”働きやすさをつくる
- 障害の配慮事項の書き方|働きやすさを伝えるコツ
- キャリアアドバイザーから、あなたへ。
履歴書を書く際に気をつけるべきルール
障害者雇用枠での就職活動において、履歴書はあなたの第一印象を決めるとても大切な書類です。特に障がい者雇用においては、「自分の特性や配慮事項をどのように伝えるか」が、採用の可否にも大きく関わってきます。この章では、履歴書を書くときに押さえておきたい基本的なルールやマナーを解説します。
1. 書式の統一を心がける
まずは履歴書のフォーマットです。市販のテンプレートや、厚生労働省のホームページでダウンロードできるフォーマットなどを使うと安心です。フォーマットは自由に変更できることもありますが、あまりに独自のものを使用すると、かえって読みづらくなることも。見やすさや読みやすさを意識し、フォントや文字サイズ、記入スタイルは統一しましょう。
2. 黒のボールペンかパソコン入力が基本
手書きの場合は、黒のボールペンで丁寧に書きましょう。修正液や修正テープの使用はNGです。訂正が必要な場合は、新しい用紙に書き直すのがマナーです。パソコンで作成する場合も、全体のレイアウトが整っていて、余白や行間が適切であることが大切です。
3. 日付は提出日を記入
履歴書には必ず日付を記入しますが、これは「書いた日」ではなく、「提出する日」を書くようにしましょう。郵送で送る場合は、ポストに投函する日を記載するのが基本です。
4. 写真は最近3ヶ月以内のものを使用
写真も、第一印象に関わる大切なポイント。正面から写った、スーツ姿で表情の明るいものが好印象です。背景は白や薄い青などが無難です。証明写真機を使う場合もOKですが、できれば写真館などで撮影してもらうと、より印象が良くなります。
5. 誤字脱字・空欄はNG
誤字脱字は、読み手に「この人は丁寧さに欠けるのでは?」という印象を与える原因になります。書き終わったら、必ず見直しをしましょう。また、空欄が多いと「やる気がない」と判断されることもあります。記入が難しい項目も、一言でも自分の状況を書いておくのがおすすめです。
基本情報の書き方
履歴書の最初に記載する「基本情報」は、応募先企業があなたのプロフィールを知るための重要なパートです。ここでは、名前・住所・連絡先など、シンプルな項目が多いですが、記入ミスがないように丁寧に仕上げることが大切です。また、障害者雇用枠での応募においては、連絡手段の希望や緊急連絡先など、少し工夫が必要な場合もあります。以下にポイントを紹介します。
1. 氏名・ふりがな
名前はフルネームをはっきりと書きましょう。ふりがなは、履歴書のフォーマットによって「ふりがな(ひらがな)」か「フリガナ(カタカナ)」のどちらかに指定されている場合があります。それに合わせて正確に記入しましょう。
2. 生年月日・年齢
生年月日は西暦か和暦かを統一し、年齢も「履歴書を書く時点での年齢」を記載します。西暦で記入する場合は、他の項目も西暦で統一するのが基本です。
3. 住所
都道府県から番地、建物名・部屋番号まで省略せずに記入しましょう。郵送での連絡がある場合に備え、正確な情報が必要です。また、視覚障害や読み書きに困難がある方で、住所記入に支援が必要な場合は、事前に誰かに確認してもらうのも一つの手です。
4. 電話番号・メールアドレス
企業からの連絡がスムーズに取れるよう、必ず日中に連絡が取れる電話番号を記入しましょう。スマートフォンの場合は、メールの受信設定(PCメールが届かない設定など)も確認しておくことをおすすめします。
メールアドレスは、できるだけフリーアドレス(Gmailなど)を使い、 「------123@example.com」などビジネスにふさわしい名前に設定しておくと印象が良くなります。昔使っていたニックネームや数字ばかりのアドレスは避けましょう。
5. 連絡方法の希望(必要に応じて)
障がいの特性によって「電話での応対が難しい」「聞き取りにくい」などがある場合は、メールやFAXなど、希望する連絡方法を備考欄に一言添えておくと安心です。例:「お電話がつながりにくいため、できるだけメールでご連絡いただけると助かります」など。
6. 緊急連絡先(任意)
家族や支援者など、緊急時に連絡を取ってもらいたい人の情報も、任意で記入することがあります。特に就労移行支援事業所を利用している場合は、担当スタッフの連絡先を記載してもよいケースもあります。
履歴書の基本情報欄は、一見シンプルですが、企業側があなたとスムーズに連絡をとるための大事な情報源です。丁寧さ・正確さ・配慮を意識して記入することで、信頼感のある履歴書になります。
学歴・職歴の書き方|正しく・丁寧に伝える履歴書作成のコツ
履歴書の「学歴・職歴」欄は、あなたのこれまでの歩みを伝える大切な項目です。
特に障害者雇用枠での応募では、過去の職歴に不安を感じてしまう方も少なくありません。
しかし、正確に、そして誠実に書くことが、信頼につながる第一歩です。この章では、学歴・職歴欄の基本的なルールと、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。
◆ 年月の記入は正確に
まずは、入学・卒業、入社・退社といった年・月の記載からスタートします。履歴書では年月を「西暦」で統一して書くのが一般的です。
例:
2015年4月 〇〇高等学校 入学
2018年3月 〇〇高等学校 卒業
のように、「年」と「月」を漏れなく、正確に記載しましょう。
書いているうちに年月のズレが起きてしまうこともあるため、下書きをしたうえで最終的に見直す習慣をつけることが大切です。
◆ 学歴の書き方:中学校は省略してもOK
学歴は通常、高等学校(高校)から記載するのが一般的です。中学校までの義務教育課程については省略しても問題ありません。
例:
2015年4月 〇〇市立△△高等学校 入学
2018年3月 〇〇市立△△高等学校 卒業
学校名は略さず、「〇〇市立」や「△△高等学校」といった正式名称で記載しましょう。特別支援学校を卒業された方は、そのままの名称で問題ありません。また、大学に進学した方は「学部名」「学科名」、さらに「留学経験」がある場合も記載すると、アピール材料になります。

スタッフ
キャリアアドバイザーのポイント
一部の求人では「高卒以上」が応募条件となっていることもあります。学歴によって応募可否が変わるケースもあるため、事前に求人票の条件をよく確認しましょう。
◆ 職歴の書き方:会社名と在籍状況を丁寧に
職歴は、これまで正社員や契約社員として勤務した企業を時系列で記載します。以下の点に注意しましょう。
正式な会社名を書く(略称NG)
入社・退社の年月を記入
退社理由を簡潔に記載する
例:
2018年4月 株式会社〇〇 入社
2020年3月 株式会社〇〇 退職(契約期間満了のため)
短期間のパート・アルバイトについては原則省略可能ですが、離職期間が長かった場合や、アルバイト経験しかない場合は記載したほうがプラスに働くこともあります。
また、派遣社員として働いていた場合には、以下のように記載しましょう。
例:
2021年6月 株式会社△△(派遣元)より株式会社□□(派遣先)に派遣
2022年3月 派遣期間満了のため退職

スタッフ
キャリアアドバイザーのポイント
保険加入歴のある勤務先は、基本的にすべて記載しましょう。正確な情報が不明な場合は、年金事務所で「被保険者記録照会」を行うことができます。うっかりした記載ミスや経歴詐称は、後の内定取り消しや解雇につながることもあるため、細心の注意を払いましょう。
◆ 現在の状況も忘れずに
履歴書の職歴欄の最後には、現在の状況を記載するのがマナーです。
現在も在職中の場合:
2021年4月 株式会社△△ 入社
(現在に至る)
既に退職している場合:
2023年5月 株式会社△△ 退職(自己都合退職)
また、就職活動中の方は「現在、就職活動中」などの一文を添えても良いでしょう。就労移行支援を利用している場合は、その旨を面接で説明する準備をしておくと安心です。
◆ 空白期間がある場合の工夫
ブランク(空白期間)がある方は、その間に何をしていたのかを履歴書ではなく職務経歴書や面接で説明できるように準備しておきましょう。たとえば、療養していた、支援機関でトレーニングを受けていたなど、前向きな取り組みを伝えられると好印象です。
◆ 最後は「以上」で締める
履歴書の職歴欄の最後には、「以上」と書いて締めくくりましょう。これは書式上のルールなので、忘れず記載してください。
学歴・職歴欄は、あなたの過去を整理し、企業に伝える大切な情報源です。「自信がない」と思ってしまう経歴も、書き方を工夫することで、しっかりとした印象につながります。
免許・資格の書き方|履歴書で強みをしっかり伝えるコツ
履歴書の「免許・資格」欄は、あなたのスキルや学びの証を伝える項目です。たとえ小さな資格でも、積み重ねてきた努力の結果です。障害者雇用枠で応募する場合も、この欄は自己PRのひとつとして大いに活用できます。
◆ 基本のルール:正式名称で、取得年月を忘れずに
資格や免許は、正式名称で記載するのが基本です。略称や通称ではなく、資格証や免許証に書かれている表記を確認して記入しましょう。
また、取得した年・月も必ず書きます。
記入例:
2019年10月 普通自動車第一種運転免許 取得
2022年3月 日商簿記検定3級 合格
2024年1月 MOS Word(Microsoft Office Specialist)合格
まだ取得見込みの資格については、
2025年6月 MOS Excel 受験予定
と書くことも可能ですが、面接時に受験の意思や準備状況を説明できるようにしておくとよいでしょう。
◆ アピールポイントとしての資格
障がいの有無にかかわらず、資格は自分の強みを補足する手段になります。特に在宅ワークやデスクワークを希望している場合は、以下のような資格が役立つケースが多いです。
パソコン関連:MOS、ITパスポート、タイピング検定など
事務系:簿記検定、秘書検定、ビジネス文書検定
コミュニケーション系:サービス接遇検定、電話応対技能検定
福祉系:介護職員初任者研修、福祉住環境コーディネーター
資格が直接業務に関係しない場合でも、「学ぶ姿勢」や「継続力」を伝える材料として有効です。

スタッフ
キャリアアドバイザーのワンポイント
「資格が少なくて不安…」という方もご安心ください。資格が多ければ良いというものではなく、職種との相性や取り組み姿勢が見られています。未取得の資格があっても、「現在勉強中です」と面接で伝えることが好印象につながります。
◆ 優先順位を考えて並べる
履歴書にはスペースの限りがあるため、取得した資格が多い場合は、応募職種に関係の深いものから順に記載するとよいでしょう。
たとえば、事務職希望ならパソコンや簿記関連を先に。介護職を目指すなら福祉系資格を上位に配置するなど、読む側が「この人はこの仕事に向いていそう」と思える順番を意識します。
◆ 国家資格・民間資格の違いを理解しておこう
資格には「国家資格」と「民間資格」があります。どちらが良い・悪いではありませんが、業務独占資格(例:看護師、電気工事士など)は国家資格であることが多く、信頼度が高いとされています。
一方、民間資格も多様化が進み、実践的な内容やトレンドに即した内容のものが多く、特定業界では評価されるケースも増えています。
◆ 資格がない場合の対処法
「これといった資格を持っていない」という方も大丈夫です。その場合は、「今後取得したい資格」「現在勉強中の分野」などを志望動機や自己PRの中で触れると、前向きな姿勢を伝えることができます。
例:
現在、在宅ワークへの就職を目指し、MOS資格の取得に向けて学習を進めています。
◆ 福祉関係の資格も忘れずに
障がいがある方の中には、福祉関連の研修やセミナーに参加している方もいます。たとえば「ピアサポーター研修修了」や「就労支援機関でのスキルアッププログラム受講」なども、履歴書の資格欄に記載できます。
これらは「意欲的に学んでいる証」として企業から評価されやすいので、ぜひ積極的に書いてみてください。
◆ 最後に「以上」で締めるのを忘れずに
資格欄も職歴と同様に、最後に「以上」と書くのが履歴書のマナーです。細かい点ではありますが、丁寧な印象を与える大切なひと手間です。
免許・資格欄は、自分が積み上げてきた努力を見える形で表すチャンスです。今はまだ少ないと思っても、これから増やすこともできます。焦らず、あなたの強みを丁寧に伝えていきましょう。
志望動機・自己PRの書き方|自分らしさを言葉にしよう
履歴書の中でも特に重要なのが、志望動機と自己PRの欄です。
どちらも「なぜこの仕事に応募したのか」「あなたはどんな強みを持っているのか」を伝える項目で、採用担当者がもっとも注目するポイントのひとつです。
障害者雇用枠で応募する場合、「配慮が必要なことがある分、自分にできることをしっかり伝えたい」と思う方も多いはず。この章では、伝えたいことをうまくまとめるコツを紹介していきます。
◆ 志望動機は「共感」と「活かせる力」で組み立てよう
志望動機は、「どうしてその企業・職種を選んだのか」という気持ちを伝える欄です。ただ「家から近いから」「在宅勤務できるから」といった理由だけではなく、その企業に共感した点や、自分の経験・スキルがどう活かせそうかも含めて書くと、説得力が増します。
例文(事務職応募の場合):
貴社の「社員一人ひとりの働きやすさを大切にする」という企業理念に共感し、志望いたしました。これまで在宅での文書作成やデータ入力の経験があり、正確さとスピードには自信があります。自分の得意を活かしながら、貴社に貢献したいと考えております。
企業研究をして、HPや採用ページに書かれている理念や働き方への取り組みなどを読んでおくと、「共感できるポイント」を見つけやすくなりますよ。
◆ 自己PRは「実体験」ベースが伝わりやすい
自己PRでは、「自分がどんな人間で、どんな力を持っているか」を伝えます。とはいえ、自信がなかったり、強みが見つからないと感じる人もいるかもしれません。そんな時は、**日常の経験や過去の仕事・学校生活の中から“工夫したこと”や“努力したこと”**を振り返ってみましょう。
例文(発達障害のある方):
私は一度に複数のことを処理するのが苦手なため、毎日のタスクをToDoリストにまとめ、ひとつずつ確実にこなす工夫をしています。以前の職場では、業務フローを整理して効率化を提案し、チームの作業時間を短縮できました。特性を理解しながら、自分なりに取り組む姿勢を大切にしています。
具体的なエピソードを入れることで、あなたの「工夫する力」「前向きな姿勢」が伝わります。
◆ 志望動機と自己PRはつなげると効果的
別々の欄ですが、内容に一貫性があるとより好印象です。たとえば、自己PRで「集中力があること」をアピールしたなら、志望動機では「コツコツ作業が求められる業務に関心がある」と書くことで、ストーリーが自然につながります。
◆ 障害のことに触れてもOK。でも伝え方に注意
障害者雇用枠で応募する場合、志望動機や自己PRに軽く触れても問題ありません。たとえば「障害がある自分でも活躍できる環境を求めている」というような記述です。ただし、障害の詳細や配慮事項は別の欄で説明するのが基本なので、ここでは簡単な紹介に留めましょう。
例文:
自分の特性上、静かな環境での作業が得意であり、集中力を活かした業務に強みを感じています。
◆ 書いたら声に出して読んでみよう
書けた後は、声に出して読んでみるのがおすすめです。「自分らしいか」「言葉にすると違和感がないか」を確認できますし、面接対策にもなります。
また、可能であれば家族や支援機関のスタッフ、キャリアアドバイザーに見てもらうのも◎。第三者の目線でフィードバックをもらうことで、より良い表現にブラッシュアップできます。
◆ 最後に:あなたらしさがいちばんの魅力
志望動機も自己PRも、「うまく書こう」と思いすぎると固くなってしまいがちです。大切なのは、「あなた自身の言葉」で「働きたいという気持ち」を伝えること。形式にとらわれすぎず、あなたの想いが伝わるよう、ゆっくり丁寧に書いてみてください。
障害についての書き方|“伝えることで”働きやすさをつくる
障害者雇用枠で応募する際、履歴書やエントリーシートで「障害の内容」や「配慮が必要なこと」について記載する欄があります。ここでは、どこまで書くべきか迷う人も多いかもしれません。
「伝えることの意味」や「どんなふうに書けばいいか」について、やさしく、わかりやすく解説します。
◆ なぜ“障害について”書く必要があるの?
企業が「障害のある方を雇用したい」と考えているときに、事前に知っておきたいのは以下のような点です。
どんな特性があるのか
どんな配慮をすると力を発揮しやすいのか
安全や業務に支障がないか
これらは「不採用の理由」になるためではなく、「どうすれば安心して働いてもらえるか」を考えるための情報です。
言い方を変えれば、きちんと伝えることで、働きやすい環境を一緒につくってもらえる可能性が高まるということ。無理せず、自分らしく働くための第一歩として「伝えること」を大切にしましょう。
◆ 記載する内容は「簡潔・事実ベース」が基本
障害のことを書くときは、病名や診断名だけでなく、「どのような困りごとがあるか」「どんな工夫で乗り越えているか」まで記載するのがポイントです。
記載例(発達障害の場合):
発達障害(ADHD)があります。複数の作業を同時に進めることが苦手ですが、タスク管理アプリを活用し、1つずつ丁寧に処理することで対応しています。
静かな環境での作業に集中力を発揮できるため、そのような環境を希望します。
このように、自分の特性と対応方法、希望する配慮まで含めると、企業側もイメージしやすくなります。
◆ 配慮が必要なことは「業務に影響のある範囲で」
「配慮してほしいこと」は、自分が働く上で無理なく力を発揮できるようにするための大切な要素です。ただし、何でも書けば良いというわけではなく、「仕事をするうえで必要な範囲」で伝えることが大切です。
例えば以下のような内容は、職場で考慮されやすいポイントです。
聴覚過敏があるため、静かな環境を希望
長時間の立ち仕事が難しいため、座り作業中心の業務を希望
指示は口頭よりも、書面やチャットの方が理解しやすい
逆に、私生活上の困難や、業務に直接関係のない配慮までは書く必要はありません。
◆ 書くのが難しいときは「支援機関」や「アドバイザー」に相談しよう
「どこまで書けばいいか分からない」「自分ではうまくまとめられない」と感じたら、就労移行支援事業所のスタッフやキャリアアドバイザーに相談するのも良い方法です。
一人で悩まず、第三者の視点を借りて、自分の言葉で伝える練習をすることが、面接にも役立ちますよ。
◆ 伝えることで“安心して働ける”未来へ
障害について書くことは、あなた自身が不安なく働くための準備でもあります。特に障害者雇用枠では、「どれくらいの配慮が必要なのか」「どんな働き方なら無理なく続けられるのか」という情報はとても重要です。
働く上で必要な配慮があるのは、決して弱みではありません。それを知った上で「あなたを採用したい」と思ってくれる企業こそ、本当にあなたに合った職場です。
障害の配慮事項の書き方|働きやすさを伝えるコツ
障害者雇用枠で応募する際には、「どのような配慮が必要か」を伝えることもとても大切です。
企業側は「障がいのある方が安心して働けるように、どんな環境を整えればいいか」を知りたいと思っています。だからこそ、「あなたが働きやすいように、どんな工夫やサポートが必要か」をきちんと伝えることが、結果的に無理なく働ける第一歩になります。
「配慮事項って何?」「どうやって書けば伝わるの?」という不安を解消するために、やさしくわかりやすく解説します。
◆ 「配慮事項」は遠慮せず、でも具体的に
まず知っておいてほしいのは、「配慮をお願いすることはわがままではない」ということ。障がいのある方にとって、配慮は“特別な優遇”ではなく、“適切なサポート”です。
たとえば、以下のような内容は、多くの職場で対応可能な配慮です。
静かな環境での作業
休憩時間の取り方の工夫(こまめに短時間の休憩を取りたい など)
書面での指示や、わかりやすいマニュアルの提供
勤務時間や通勤の配慮(混雑を避けた出社時間など)
これらは職場環境に少し工夫を加えるだけで、働く人が安心して能力を発揮できるようになる大切なポイントです。
◆ 書くときは「困りごと → 解決方法」の流れで
配慮事項を書くときには、「自分がどんな場面で困りやすいのか」「それをどうすれば働きやすくなるのか」をセットで伝えるのがポイントです。
たとえば…
- 集中力が切れやすいため、こまめな休憩があるとパフォーマンスを維持しやすいです。
- 耳からの指示が入りにくいため、業務内容をメモやチャットで共有いただけるとスムーズに理解できます。
- 人混みが苦手で体調を崩しやすいため、時差出勤や在宅勤務を希望します。
このように、「困っていること」だけでなく「対策」を併せて書くことで、企業側もより前向きに検討しやすくなります。
◆ NG例:「なんでも配慮してください」「特になし」はもったいない!
配慮事項に「特になし」と書いてしまうと、企業は「この人は配慮がいらないのかな?」と判断してしまい、本当に必要なサポートが受けられなくなる可能性があります。
また、「なんでも配慮してください」というような曖昧な表現も、企業側にとっては具体的に何をすればよいのかわからず、不安を感じる要因になります。
あなた自身が自分の働きやすい環境を理解し、それを言葉にして伝えることが、ミスマッチを防ぎ、長く安心して働くためのカギになります。
◆ 書き方のコツ
簡潔にわかりやすく書く:長すぎると読まれにくいので、1つの配慮について1〜2文でまとめる。
具体例を使う:「静かな環境」や「短時間の休憩」など、職場での対応がイメージしやすい表現にする。
自分で工夫していることも伝える:「こうすれば働きやすい」という工夫を伝えることで、前向きな印象になります。
◆ 「書類に書くのが不安…」というときはどうする?
配慮事項を書くのが難しい、面接で直接伝えたい、という場合もあります。その場合は、履歴書の備考欄などに「配慮事項については面接時にお伝えしたいです」と書いておくのもOKです。
ただし、まったく伝えずに選考が進むと、配属先での困難が起きてしまうことも。可能であれば、履歴書やエントリーシートのどこかに要点だけでも記載しておくのが安心です。
◆ あなたの働きやすさを大切に
配慮事項を伝えることは、「安心して働ける環境づくりのスタート」です。あなたが無理せず、長く続けられる職場に出会うためにも、自分自身の“働きやすさ”を言葉にしてみましょう。
キャリアアドバイザーから、あなたへ。
履歴書を書くという作業は、誰にとっても簡単なことではありません。とくに障がいをお持ちの方の場合、「どう伝えればいいか」「正直に書いて大丈夫だろうか」と不安を感じることもあると思います。
でも、大丈夫です。
あなたのこれまでの経験や、日々積み重ねてきた努力には、必ず価値があります。
障がいの有無にかかわらず、誰もがそれぞれのストーリーを持っていて、その中には“あなたらしさ”がたくさん詰まっています。
履歴書は、ただの紙ではなく、あなたの人柄や想いを伝えるツールです。「うまく書けない」と思っても、焦らなくて大丈夫。一緒に、ゆっくり整えていけばいいんです。
私たちキャリアアドバイザーは、履歴書の添削はもちろん、「こんなふうに伝えると、あなたの良さがもっと伝わりますよ」といったアドバイスもおこなっています。必要な配慮の伝え方や、不安に感じることがあれば、ぜひ相談してください。
あなたが自分らしく働ける場所は、きっと見つかります。自分の強みと向き合いながら、一歩ずつ進んでいきましょう。私たちは、いつでもあなたの味方です。

スタッフ
障がいのある方のための、在宅就職・転職支援サイトサービス
「障がい者のための在宅就労求人.com」では求人紹介だけではなく、障害者雇用における転職活動ノウハウもサポート。詳しくはこちら。
スタッフコラムのおすすめ記事
-
2025/12/10
大人の発達障害(神経発達症)の理解と効果的な対策
-
2025/05/20
障がい者雇用の魅力的な職種とは?求人の種類とおすすめのお仕事
-
2025/05/20
障がいがあっても大丈夫。自分らしい働き方を家族と一緒に見つけよう
-
2025/05/20
どんな人でも自己分析は内定への近道