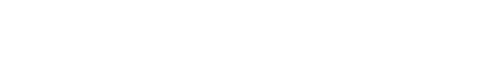2025/11/13
障害者雇用って実際どう?メリット・デメリットと、自分に合った働き方の探し方

スタッフ
こんにちは!障がい者のための在宅就労求人.comです。
今日は障害者雇用制度についてお話していきます。
目次
"障害者雇用制度とは?
障がいがある人も、自分らしく働くことができるように──
そんな思いから生まれたのが「障害者雇用制度」です。この制度は、障がいのある人が仕事の場で不利にならないように、企業が雇用の機会や働きやすい環境を提供することを、法律で定めたものです。
◆ 障害者雇用促進法とは?
障害者雇用制度の根拠となるのが、正式には「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」という法律です。この法律により、一定以上の規模の企業には、障がいのある人を一定の割合で雇う義務があります。
2024年4月時点での雇用義務の割合は以下のとおりです:
民間企業:2.5%(2026年には2.7%へ引き上げ予定)
国・地方公共団体:2.6%
教育委員会:2.5%
例えば、従業員が40人いる企業は、1人は障害者雇用枠で雇う義務があるということです。
企業がこの義務を果たさない場合、「障害者雇用納付金」という形でペナルティが課されることもあり、国全体として障がい者雇用を促進する仕組みが整っています。
◆ 障がいのある人が安心して働くためのサポート制度も
制度として整っているのは雇用義務だけではありません。障がいのある人が安心して働けるように、さまざまな支援が用意されています。
たとえば:
ハローワークでの専門相談員の配置
就労移行支援など福祉サービスとの連携
職場実習制度
ジョブコーチ制度(職場定着支援)
また、企業側も「合理的配慮」を提供することが求められています。合理的配慮とは、障がいのある人が業務を行いやすいように環境を整えたり、業務内容を調整したりすることです。
◆ 「障害者雇用枠」の求人とは?
障害者雇用制度に基づいて出される求人の多くは、「障害者雇用枠」と呼ばれる特別な枠での採用です。この枠では、応募時に障害者手帳の提示が必要になる場合が多く、書類選考や面接でも「配慮事項」について相談ができる環境が整っています。
さらに、在宅ワークOKの障害者雇用枠の求人も増えてきています。パソコンを使った事務作業やデータ入力、カスタマーサポートなど、体調や通勤への不安がある人でも、安心してチャレンジできる働き方が広がりつつあります。
◆ 制度を知ることが、第一歩になる
「障害者雇用制度って難しそう」と感じる方もいるかもしれません。でも、制度を知ること=自分らしい働き方を選ぶ第一歩になります。
この制度があることで、「安心して働ける場所がある」と思えることは、就職活動を前向きに進めるための大きな支えになるはずです。"
"障害者雇用と一般雇用との違いは?
就職活動をするうえで、まず考えるべきなのが「一般雇用枠で応募するか、それとも障害者雇用枠で応募するか」ということです。どちらにもメリット・デメリットがあるため、違いを理解したうえで、自分に合った働き方を選ぶことが大切です。
◆ 選考のプロセスや配慮の有無が違う
一般雇用では、基本的に健常者と同じ基準で選考が行われます。応募の際に障害があることを伝える必要もないため、障害への配慮は基本的にありません。
一方、障害者雇用枠では、障害の特性に配慮した採用面接や勤務環境の整備が前提となっています。
たとえば以下のような違いがあります:
比較項目 一般雇用 障害者雇用
応募書類 特に配慮なし 障害についての記載や配慮事項を書く欄があることも
面接 一般的な質問が中心 障害内容・配慮の必要性についての質問が含まれる
入社後の環境 一般基準 障害に応じた配慮(例:作業環境・勤務時間・業務内容の調整など)あり
◆ 業務内容や職種の幅にも差がある
一般雇用では、職種の選択肢が幅広く、キャリアアップの機会も多いのが特徴です。営業、企画、エンジニア、マーケティングなど、あらゆる分野に挑戦できます。
一方で障害者雇用枠では、比較的業務内容が限定されている場合が多いのが実情です。
よくある職種としては:
データ入力
書類整理
軽作業
清掃業務
在宅ワーク(事務サポート、カスタマー対応など)
ただし最近では、スキルや希望に合わせて多様な仕事に就ける障害者雇用枠の求人も増加中です。特にIT分野やデザイン、リモートワークOKの事務職なども選べるようになってきています。
◆ 給与・昇進制度にも違いがあることも
一般雇用では、基本的に成果主義や職責に応じた給与体系となっています。一方、障害者雇用では、体調への配慮や勤務時間の短縮などもあるため、給与水準が一般枠より低い場合があるのも事実です。
また、企業によっては昇進・昇給のチャンスが限られているケースもありますが、これも徐々に改善が進んでいます。
◆ 在宅ワークの選択肢が広がっているのは障害者雇用の強み
以前は「出社して当たり前」だった働き方も、現在は変わってきました。特に障害者雇用枠では、在宅勤務を前提とした求人が多く見られるようになり、「通勤が難しいから働けない」という悩みを持つ方にとって大きな希望となっています。
たとえば、発達障害を持つAさんは、通勤によるストレスが強く出てしまうことから、完全リモートの事務職に就職。チャットツールやマニュアルを使った業務で、自分のペースを守りながら働けるようになり、職場への定着率も高まりました。
◆ どちらが良い・悪いではなく「自分に合っているか」が大事
「障害者雇用と一般雇用、どっちがいいの?」とよく聞かれますが、**答えは“人それぞれ”**です。
安定した環境で長く働きたい → 障害者雇用枠
スキルを伸ばしてキャリアアップしたい → 一般雇用枠
体調や生活状況に合わせて柔軟に働きたい → 在宅ワークのある障害者雇用枠
こんなふうに、自分に合った働き方を選ぶことが大切です。そのためにも、自己分析を通して「自分はどう働きたいのか」「どんな環境が合っているのか」をしっかり考えていきましょう。"
"在宅ワークという働き方──障害者雇用で広がるキャリアの選択肢【実例紹介】
「外に出るのがむずかしい」「毎日決まった時間に通勤するのは体力的にキツい」。
そんな悩みを持つ人にとって、在宅ワークという選択肢は、まさに“自分らしく働く”ための大きな一歩になります。
ここでは、障害者雇用の枠で実際に在宅ワークをしている人の事例を通じて、どんな可能性があるのかを見ていきましょう。
◆ ケース①:発達障害+感覚過敏のAさん|集中できる在宅環境で才能開花
Aさんは、20代後半の男性。発達障害の特性として「聴覚過敏」や「マルチタスクが苦手」といった課題を抱えていました。以前は一般雇用枠で営業職に就いていましたが、オフィスの雑音や会話の多さで業務に集中できず、半年で退職。
その後、障害者雇用枠の在宅ワーク求人に出会い、現在はIT企業のデータ入力業務を担当しています。
▶ ポイントは「静かな環境 × 得意を活かせる仕事」
Aさんは自宅の静かな部屋で、自分のペースで一つひとつの仕事に集中できるようになりました。もともとタイピングが得意だったこともあり、精度の高い作業を継続できており、職場からの評価も高いそうです。
「“マイナス”と感じていた特性が、“この仕事なら活きる”って思えるようになりました。」
◆ ケース②:身体障害+車いすユーザーのBさん|在宅でカスタマーサポート職に就職
Bさんは40代女性。車いす生活をしており、公共交通機関での移動が負担になっていました。介助者が必要な時間帯もあるため、フルタイムの出社は不可能という状況でした。
ハローワークで紹介された障害者雇用枠の在宅カスタマーサポート業務に応募し、見事採用に。
▶ 自分のリズムを守れるから長く働ける
勤務時間は1日5時間、週4日からスタート。顧客との電話やチャット対応が中心で、自宅から業務マニュアルとツールを使って応対します。
職場では定期的にオンライン面談があり、困ったときはすぐ相談できる体制があるのも安心ポイントだとか。
「“会社のために無理する”から“自分に合わせて会社とつながる”働き方へ。今は仕事も生活も楽しめています。」
◆ ケース③:精神障害+気分の波があるCさん|柔軟な業務時間で安定就労
Cさんは30代男性。双極性障害(躁うつ病)を抱えており、体調に波があるため、安定して出社するのが難しい状態でした。
就労移行支援を通じて、完全在宅・フレックスタイム制のWebライター職に挑戦。はじめは文章を書くのが不安だったそうですが、得意な趣味ジャンル(アニメ、ガジェット)に関する記事を書くうちに評価され、現在は副編集長として活躍中です。
▶ 得意を活かす×体調に合わせた働き方
朝がつらい日は昼から仕事を始めるなど、自分の体調に合わせて働ける環境があることで、長く続けられるようになったといいます。
「“毎日同じ時間に働くのが普通”って思っていたけど、今の仕事を知って、自分のペースでいいんだって初めて実感しました。」
◆ 自己分析が在宅ワークを見つけるカギ
これらの事例に共通するのは、「自分の得意・不得意を見つめなおした結果、働き方が変わった」ということです。
静かな環境の方が集中できる → データ入力や文字起こし
会話が得意 → カスタマーサポートやチャット対応
文章を書くのが好き → Webライター、編集、SNS運用
つまり、自己分析を通して「自分に向いている働き方・職種」を理解することが、在宅ワークという選択肢につながるんです。"
"障害者雇用のメリット──“自分らしい働き方”が実現しやすい制度
障害者雇用制度には、「自分の特性に合った働き方を見つけやすい」「サポート体制が整っている」など、多くのメリットがあります。ここでは、自己分析を活かして就職活動を進めたい方にとっての「障害者雇用の強み」を、わかりやすく紹介します。
◆ 一般雇用よりも就職しやすい傾向がある
まず大きなメリットの一つが、企業にとって障がい者雇用が“義務化されている”制度であることです。
法定雇用率が設けられており、一定数の障がい者を雇用することが企業に求められています。そのため、一般雇用枠と比較して、以下のような特徴があります:
求人が非公開で支援機関に集まっている場合も多い
就労移行支援などのサポートを受けながら活動できる
選考過程で合理的配慮を受けられる
自己分析をしっかりして、自分の「できること」「配慮が必要なこと」を整理しておけば、よりマッチした職場と出会いやすくなります。
◆ 職場でのサポートと合理的配慮
障害者雇用のもうひとつの強みは、「働くうえでの困りごと」を事前に相談できる環境があることです。
たとえば、以下のような**“合理的配慮”**を企業に求めることができます。
通院などによる勤務時間の調整
静かな場所での業務配置(感覚過敏の方など)
指示の出し方の工夫(口頭ではなくチャットでなど)
作業工程をわかりやすく見える化する
上司や同僚との定期的な面談サポート
これらは、**自己分析を通して「どんな配慮があると働きやすいか」**を把握できていれば、応募時や面接時に伝えることができます。
在宅ワークにおいても、配慮の内容は重要です。たとえば「Zoomの会話は疲れるのでチャット中心にしたい」「勤務時間に波があるので柔軟にしたい」など、しっかり伝えることで長く働ける環境が作れます。
◆ キャリア形成と自立支援の機会
「障害者雇用=単純作業だけ」と思われがちですが、実際はスキルアップやキャリア形成につながる職場も増えています。特に在宅ワークを活かせる以下のような分野では、専門性が高まるにつれて、収入や役割もアップします。
Webライター、編集者
デジタルマーケティング
プログラマー、Web制作
オンライン事務、SNS運用
電話・チャットのカスタマーサポート
また、働きながら「資格取得を支援してくれる」「eラーニング環境が整っている」といった職場も多くなってきました。
自己分析で「好きなこと」「伸ばしたいスキル」を明確にすることは、障がい者雇用でのキャリア形成においてとても有効です。
◆ 障がい者雇用枠だからこそ、選べる“働きやすさ”
制度の力を借りて「働きやすさ」を選べるのが障がい者雇用の魅力です。
通勤が難しければ在宅勤務
フルタイムが難しければ短時間勤務
不安なことは支援機関を通して事前相談
自分らしい働き方の第一歩として、「自己分析+障害者雇用」という組み合わせは、とても相性が良いといえるでしょう。
"
"障害者雇用のデメリット──理想と現実のギャップも知っておこう
障害者雇用は、自分に合った働き方を実現できる大きなチャンスです。しかし、すべてが「理想どおり」とは限らないのも現実。制度の仕組みや社会の変化は進んでいるものの、まだ課題も残されています。ここでは、障害者雇用のデメリットや気をつけたいポイントを、自己分析と絡めながら解説します。
◆ 職種の選択肢が少ないと感じることがある
障害者雇用枠では、「事務補助」「清掃」「軽作業」といった比較的サポートしやすい業務が中心になっている企業も少なくありません。
「もっと専門性を活かしたい」「自分のスキルを評価してもらいたい」と思っても、募集されている仕事にミスマッチを感じてしまう方も多いです。
ただし、これは自己分析をしっかり行うことでカバーできる面もあります。
「どんなスキルがあるか」
「どんな働き方なら継続できるか」
「今の自分に足りない経験は何か」
を整理することで、「職種が限られている」環境でも、自分に合うポジションを見つけたり、将来的にスキルアップの道を模索したりすることができます。
◆ 障害者手帳を取得する必要がある
障害者雇用枠で働くには、基本的に「障害者手帳」の取得が必要です。これは精神・身体・知的いずれの場合も同じです。
診断名があっても手帳がないと応募できない
取得までに時間がかかることがある
「障害者手帳を持っている」と伝えることに心理的抵抗がある
という声もよく聞かれます。
ただし、これは逆に言えば、制度の後ろ盾があることで安心して働ける職場を選べるということでもあります。自己分析を通して「自分がどんな支援を受けたいのか」「なぜ手帳を取得するのか」を整理しておくと、手帳の必要性に納得が持てるようになるかもしれません。
◆ キャリアアップできる機会が少ないと感じる場合もある
「障害者雇用=補助的業務」という見方が根強く残っている職場も存在します。そのため、責任ある仕事を任されにくかったり、評価が上がりにくかったりするケースも見られます。
「ずっとこのままの仕事内容かな…」と不安になる人も少なくありません。
しかし、これも自己分析で「どこまでの責任を求めているか」「どんな働き方が将来的にしたいか」を明確にすることで、企業選びの基準が見えてきます。近年では、以下のような“キャリア志向のある障がい者向け”求人も増加中です。
在宅ワークで専門職としてスキルアップ
スタートアップ企業でのオンライン勤務
マネジメント職やリーダー候補の求人
また、就労移行支援事業所やキャリアカウンセラーのサポートを活用すれば、より成長を目指せる環境に出会える可能性も高まります。
◆ “制度の枠”に頼りすぎない視点も大事
制度はあくまでも「サポート」であり、最終的に働き方を決めるのは“自分自身の選択”です。障害者雇用枠での就職を選ぶにしても、
自分はどんな職場で輝けるのか?
どんなサポートがあれば自立できるのか?
将来的にはどんな生き方をしたいのか?
といった視点で自己分析をしていくことが、何より大切です。"
"一般雇用から障害者雇用へ転換した障害当事者の成功ストーリー
障害者雇用は、特別扱いではなく、自分のペースで働ける環境を整えるための手段です。ここでは、一般雇用から障害者雇用へ転換した方々の実際の成功事例を紹介し、どのようにして自分らしいキャリアを築いたのかを具体的にお伝えします。
◆ 事例1:在宅ワークでキャリアを積んだAさん
Aさんは、もともと大手企業の営業職に従事していました。ところが、うつ病の影響で出社が難しくなり、業務にも支障をきたすようになりました。初めは休職していましたが、次第に復職が難しくなり、転職を決意。しかし、一般の求人市場では自分に合った職場を見つけるのが難しく感じていました。
その後、Aさんは障害者雇用枠を活用することにしました。在宅勤務の求人に出会い、自分の特性を理解してくれる企業と出会うことができました。
自己分析:自己分析を行い、Aさんは「通勤ができないこと」「精神的なサポートが必要であること」を明確にし、それに合った求人を探しました。
サポート:企業は柔軟に勤務時間を調整し、カウンセリングやメンタルサポートを提供してくれたため、Aさんは自分のペースで仕事を進められました。
Aさんは現在、在宅ワークのWebライティングとデータ入力を担当しています。最初は少ない業務量からスタートしましたが、徐々に業務範囲が広がり、今ではフルタイムで働けるようになりました。
◆ 事例2:障害者手帳を活用し、キャリアアップを果たしたBさん
Bさんは、身体的な障害を持ちつつも、以前は一般雇用でフルタイム勤務をしていました。ところが、長時間の立ち仕事が難しくなり、体調を崩してしまいました。医師からは労働時間の短縮を勧められ、仕事を辞めることに決めました。
その後、Bさんは障害者雇用の枠内で、フルタイムではなく、柔軟な勤務が可能な職場を見つけました。Bさんは障害者手帳を取得し、障害者雇用枠での仕事探しを始めました。
自己分析:Bさんは「体調を崩さないようにするための働き方」を重視し、短時間勤務の在宅ワークを希望しました。また、仕事の内容も体を使わないものを選びました。
サポート:障害者雇用枠を活用した企業では、Bさんの体調に合わせた柔軟な働き方を提案してくれ、安定した環境で働くことができました。
その結果、Bさんは健康を保ちながら、業務内容を事務職からITサポートへとキャリアアップ。今では自宅でサポート業務を行いながらも、定期的にスキルアップのための勉強をして、ITの専門知識を深めています。
◆ 事例3:職場環境に適応し、自立を実現したCさん
Cさんは、発達障害を持ちながらも、長年大手企業で働いていました。しかし、社内での人間関係やコミュニケーションに苦しむことが多く、退職を決意しました。その後、就労移行支援事業所を利用し、障害者雇用枠での転職を目指しました。
自己分析:Cさんは自分の「コミュニケーションの苦手さ」を明確にし、職場環境においてどのような配慮を求めるかを考えました。
サポート:就労移行支援事業所では、職場での支援や面接練習を通じて、Cさんのコミュニケーションスキルを高めました。その結果、障害者雇用枠でカスタマーサポートの仕事を見つけることができました。
最初は業務量に不安もありましたが、**企業側の配慮(静かな環境、マニュアル化された業務フロー、週1回の面談サポート)**があったおかげで、仕事に慣れることができました。現在、Cさんは自立した生活を送りながら、着実にキャリアアップしています。
◆ 成功のカギは自己分析とサポートの活用
これらの事例からわかるように、障害者雇用への転換は、単に「障がいを持っているから仕方なく選ぶ」のではなく、自分のライフスタイルに合った働き方を実現するための一つの選択肢として活用できます。
自己分析を通じて、自分に合った職場や働き方、サポートを理解し、上手に活用することで、無理なくキャリアを築くことが可能です。"
"まとめ──自分に合った働き方を見つけるために
これまで、障害者雇用の制度やメリット、デメリットを掘り下げてきました。ここでは、改めて障害者雇用の選択肢をどう活用し、自分に合った働き方を見つけるためのポイントを整理していきます。
障害者雇用制度は、障がいを持つ方々にとって、多くの可能性を広げる手段となる一方、まだまだ克服すべき課題も残されています。しかし、自分の特性や希望を理解し、しっかりと自己分析を行うことで、最適な働き方が見えてくるということを多くの成功事例が示しています。
◆ 障害者雇用は自分らしい働き方を実現するための一つの手段
障害者雇用は、ただの「特別枠」というわけではなく、自分に合った働き方を実現するための柔軟な選択肢です。制度をうまく活用することで、以下のようなメリットがあります。
合理的配慮:自分の障害に合わせて、勤務時間や作業環境を調整してもらえる
サポート体制:面接や就業後の支援が受けられるため、長期的に安定して働きやすい
キャリア形成のチャンス:自分に合った職場で経験を積むことで、キャリアアップや自己実現が可能
障害者雇用枠での求人が増加している今、自己分析を行い、「自分の強み」と「働きやすい環境」を見極めることが何より重要です。
◆ 自己分析がカギ
自己分析を通じて自分がどんな仕事に向いているのかを理解することが、成功するための大きなポイントとなります。自分の得意なことや興味があること、逆に苦手なことを把握することで、無理なく続けられる仕事を見つけることができます。
例えば、
得意なスキルや経験を活かせる職種を見つける
自分に必要なサポート(勤務時間、作業環境、コミュニケーションスタイルなど)を整理し、適切な配慮を求める
キャリアプランを描き、長期的にどんな働き方をしたいのかを考える
このように、自己分析は「何をしたいのか」「どんな働き方が合うのか」を明確にするための基盤です。自己分析をしっかり行うことで、障害者雇用枠でも自分らしい仕事を見つけやすくなります。
◆ 障害者雇用のデメリットを理解し、準備する
もちろん、障害者雇用にはデメリットもあります。職種の選択肢が限られていること、障害者手帳が必要であること、キャリアアップの機会が少ないと感じることなど、実際に課題として挙げられます。しかし、これらは事前に知識として備えておくことで、無駄な不安を感じずに次のステップを踏むことができます。
職種が限られている場合:自己分析を通じて、自分に合った業務を見つけ、将来的なキャリアアップの目標を持つこと
障害者手帳を取得する必要がある場合:手帳取得のプロセスやメリットを理解し、自分の障害に合った手帳を取得する準備をすること
キャリアアップが難しい場合:自分のスキルアップや勉強を続けること、就業支援機関やサポートを活用すること
障害者雇用の制度を理解した上で、自分の希望に合った職場を選び、足りないスキルを補う努力をすることで、キャリア形成は十分に可能です。
◆ 自分に合った働き方を探すために
最終的に、自分に合った働き方を見つけるためには、以下のようなことを意識して行動することが重要です。
在宅ワークやフレックスタイム制など、自分のライフスタイルに合わせた働き方を積極的に選択する
職場環境やサポート体制が自分の障害に合わせて整えられているかを確認する
キャリア支援やスキルアップの機会を活かし、自分の成長を促進する
障害者雇用は、決して一つの選択肢ではなく、柔軟に自分に合った方法を選び取ることができる制度です。自分自身の強みを活かし、障害者雇用枠を有効に活用していくことで、より充実した働き方が実現できるでしょう。
◆ 障害者雇用の未来とこれからの働き方
近年、障害者雇用は社会全体で進展を見せ、ますます多様な選択肢が広がっています。企業側も障がいを持つ方々を積極的に雇用し、多様性を尊重する働き方が増えてきています。そのため、今後は障害者雇用枠で働くことが「特別」ではなく、通常の選択肢の一つとして認識されるようになるでしょう。
今、自分にとってベストな働き方を見つけるために、制度を活用し、自己分析をしっかり行っていくことが大切です。これからの時代、障害者雇用はただの枠ではなく、あなたの能力と適性を最大限に発揮できる舞台を提供する手段となります。"
スタッフコラムのおすすめ記事
-
2025/12/10
大人の発達障害(神経発達症)の理解と効果的な対策
-
2025/05/20
障がい者雇用の魅力的な職種とは?求人の種類とおすすめのお仕事
-
2025/05/20
障がいがあっても大丈夫。自分らしい働き方を家族と一緒に見つけよう
-
2025/05/20
どんな人でも自己分析は内定への近道