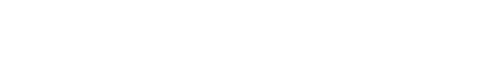2025/08/27
発達障害を持つ自分が、自分らしく働くためのヒントとステップアップの方法

スタッフ
こんにちは!障がい者のための在宅就労求人.comです。
今日は自分らしく働くためのヒントについてお話していきます。
目次
- 発達障害と働くこと
- 発達障害の特性を知ろう
- 自分に合った仕事を見つけるには?
- 発達障害者の働き方
- ステップアップを目指すためにできること
- 働きやすくなるための「配慮事項」の伝え方
- 自己理解が道を開いた。発達障害の当事者が見つけた“自分らしい働き方”
- 自分らしいキャリアの描き方
発達障害と働くこと──不安や迷いがあっても大丈夫
「仕事って、みんなが普通にできるものなんだろうか」
「自分だけ、なんでうまくいかないんだろう」
そんなふうに感じたことはありませんか?
発達障害を持つ人の中には、職場での人間関係や作業の進め方でつまずきやすかったり、感覚の過敏さや集中力の波に悩んだりする人が少なくありません。特に、「ちゃんとやらなきゃ」と思えば思うほど、うまくいかなくて落ち込んでしまう…というケースも多いです。
でも、ひとつ言えるのは――
あなたが困っているのは、「あなたのせい」ではないということ。
そして、あなたには、あなたに合った働き方があるということです。
働くこと=「正社員でフルタイム」だけじゃない
よくある誤解のひとつに、「働くって、会社に通って、決まった時間にフルで働くこと」というイメージがあります。でも、実際のところ、そんな働き方だけが正解ではありません。
最近では、在宅ワークや短時間勤務、フレックス制度を活用した働き方など、さまざまなスタイルが広がっています。発達障害のある方にとっては、こういった多様な働き方の選択肢が、「自分に合った働き方」を見つけるカギになることもあります。
たとえば:
通勤のストレスが少ない在宅勤務
静かな環境で集中できるテレワーク
対人のストレスが少ないバックオフィス業務
自分のペースで取り組めるライティングやデザイン
こういった働き方は、発達障害の特性を持つ人が、ストレスを減らしつつ、能力を活かして働ける場として注目されています。
発達障害だからこその「強み」もある
ついつい「できないこと」に目がいきがちですが、発達障害を持つ人の中には、以下のような「強み」を持っている方も多いです。
興味のあることに対しては、高い集中力を発揮できる
細かい作業やルーティン業務を正確にこなせる
独自の視点や発想で、クリエイティブな仕事に強い
「できない自分を直す」のではなく、「得意なことを活かして働く」という考え方にシフトすることで、自分らしい働き方が見えてきます。
まずは「知ること」から始めよう
「今すぐ働きたい」人も、
「働けるか不安…」という人も、
「今の働き方にモヤモヤしている」人も、
どこかに、きっとヒントが見つかるはずです。
無理せず、自分のペースで。
あなたの「働く」を、ここから一緒に考えていきましょう。
発達障害の特性を知ろう ──「自分を知る」ことが働きやすさの第一歩
発達障害とひと口に言っても、その特性や感じ方は人によってさまざまです。
まずは、自分自身の傾向を知ることが、「どんな働き方が合っているか」を見つける第一歩になります。
「苦手なこと」にばかり目を向けていると、自信がなくなってしまいますよね。
でも、それと同時に「得意なこと」や「心地いい環境」も一緒に探っていくことで、もっと自分らしい働き方に近づいていけます。
発達障害に多い特性とは?
発達障害には、主に以下のような特性があります。
注意が散りやすい/集中しすぎてしまう
音や光、匂いなど感覚の過敏さ
人とのコミュニケーションでの戸惑い
物事の段取りが苦手、マルチタスクが苦手
こだわりが強く、変更にストレスを感じやすい
こうした特性は、職場の環境や業務内容によっては困難を感じる原因になることがあります。
でも、「特性=弱み」ではない
たとえば、静かな場所で集中して作業するのが得意な方にとって、「障がい者 テレワーク」という選択肢はとても相性が良い働き方です。
・対人コミュニケーションが少ない
・自分のペースで働ける
・スケジュールの調整がしやすい
・感覚の過敏さをコントロールしやすい
こうしたメリットがあるテレワークは、発達障害の特性を持つ方にとって「ストレスを減らし、自分の力を活かせる働き方」として注目されています。
「自分の取扱説明書」をつくってみよう
自分の特性や得意・不得意を整理するには、紙やメモアプリを使って「自分の取扱説明書」を作ってみるのもおすすめです。
集中できる時間帯は?
苦手な作業はどんなもの?
ストレスを感じる場面は?
どんな環境なら安心できる?
こうしたポイントを整理しておくことで、「どんな仕事・職場が合いそうか」が見えてきます。
また、「障がい者 テレワーク 求人」などで仕事を探すときも、自分に合う条件がはっきりしていると、マッチしやすくなります。
障がい者テレワークを選ぶことで、自分の特性に合った働き方を
テレワークは、誰にとっても快適な働き方というわけではありません。でも、発達障害のある方にとっては、「無理せず働ける選択肢」としての可能性が大きい働き方です。
「音が静かな環境で集中したい」
「人との会話よりチャットのほうが気楽」
「自分のタイミングで休憩を取りたい」
そう思っているなら、きっとテレワークの働き方はフィットします。
そして、「障がい者 テレワーク 求人」は、今どんどん増えてきています。
自分に合った仕事を見つけるには? ──「できること」から始めてみよう
「自分にできる仕事ってなんだろう?」
「求人を見ても、どれが自分に合っているのかわからない…」
そんなふうに悩むこと、ありますよね。特に発達障害の特性があると、「得意・不得意」がはっきりしていることも多く、仕事選びに迷ってしまう人も少なくありません。
でも大丈夫。最初から完璧な答えを見つけなくても、「自分に向いているかもしれない」と思える仕事から、少しずつ始めていけばいいんです。
「障がい者 テレワーク」求人の選び方
最近では、発達障害や他の障がいを持つ方のために、テレワークに対応した求人が増えてきました。
「障がい者 テレワーク 求人」と検索すれば、在宅で働ける仕事を取り扱っている求人サイトもたくさんあります。
たとえば、こんな職種があります:
データ入力やアンケート処理などの事務サポート
ECサイトの商品登録、チェック作業
ブログ記事やSNS投稿のライティング
メール対応やカスタマーサポート(チャット対応含む)
Webデザインやイラスト作成(スキルがあれば)
中には、特定の資格や経験がなくても始められる仕事も多く、最初の一歩としてちょうどいいものが見つかることもあります。
ポイントは「好きな作業」や「落ち着ける働き方」
求人を選ぶときに意識したいのが、「何ができるか」だけでなく「どんな作業が苦じゃないか」「どんな環境なら続けられそうか」という視点です。
たとえば…
細かい作業が好き → データ入力やチェック業務が向いているかも
コミュニケーションが苦手 → 一人作業中心の仕事が安心
決まったルーティンの方が安心 → 定型業務が合う可能性大
特に「障がい者 テレワーク」の求人は、業務がある程度パターン化されていたり、サポート体制が整っている企業も多いため、発達障害のある方にとっても始めやすいものが多いです。
就労支援サービスの活用もおすすめ
どうしても「自分で探すのが不安…」というときは、障がい者の就労支援サービスを使うのもひとつの手です。
自分に合った仕事を一緒に探してくれる
面接の練習や書類作成のアドバイスが受けられる
実際のテレワーク業務を体験できる訓練もある
こういったサポートを受けながら探すと、「障がい者 テレワーク 求人」の中から、より自分に合ったものを見つけやすくなります。
少しずつ、「できること」を積み重ねていこう
最初から「これは天職だ!」と思える仕事に出会える人なんて、実は多くありません。
だからこそ、まずは「今できそうなこと」から始めてみるのが大切です。
そして、少しずつ「できたこと」が増えていくと、自然と次のステップが見えてきます。
在宅で働ける「障がい者 テレワーク 求人」は、そんな“はじめの一歩”にぴったりな選択肢です。
発達障害者の働き方 ― 自分に合ったスタイルを見つける
発達障害があると、職場でのコミュニケーション、マルチタスク、感覚過敏など、一般的な働き方の中でさまざまな困難に直面することがあります。でも、それは「働けない」という意味ではありません。「働き方を選べる時代」だからこそ、自分の特性に合った方法で働く道が開かれているのです。
テレワークという選択肢がもたらす自由
最近では「障がい者 テレワーク」という求人が増え、在宅勤務が可能な環境が整ってきています。発達障害のある人にとって、これはとても大きなメリットです。
たとえば、
人の多いオフィスでは集中しづらい
毎日の通勤がストレスになる
人間関係で疲れやすい
こうした課題が、テレワークであればかなり軽減されます。自宅で働くことによって、静かな環境で自分のリズムを大切にしながら、仕事に取り組むことができるのです。
得意を活かせる職種を選ぶ
発達障害の特性は「苦手なこと」だけではなく、「得意なこと」がはっきりしている場合も多いです。たとえば:
数字に強い → データ入力、経理補助
文章を書くのが好き → ライティング業務
一人で集中するのが得意 → プログラミング、Web制作
こういった強みは、テレワーク向けの仕事に活かしやすい傾向があります。「障がい者 テレワーク 求人」では、業務内容が明確で、成果ベースで評価されることも多いため、「途中でペースを乱されたくない」「自分のやり方で進めたい」と感じる人にとっては、非常に働きやすい環境です。
自分の「働き方のスタイル」を作る
発達障害を持つ人にとって、ルールやマニュアルが曖昧な仕事は不安の原因になりやすいですが、逆に「自分でルーティンを作る」ことが得意な人もいます。テレワークは、そうした自己管理能力を活かすのにぴったりのスタイルです。
毎朝決まった時間に業務を始める
25分作業+5分休憩のポモドーロテクニックを活用
タスク管理アプリで1日の予定を見える化
こうした工夫によって、「自分に合った仕事のペース」を見つけることができます。
働く=自立ではなく、「自分らしく暮らす」こと
発達障害を持つ人にとって、働くことはただの「経済的自立」ではなく、「自分らしい暮らし方を築くための手段」でもあります。
だからこそ、「みんなと同じように」ではなく、「自分に合った働き方」を選ぶことがとても大切です。障がい者テレワークという選択肢は、その実現を後押ししてくれる手段のひとつなのです。
ステップアップを目指すためにできること
発達障害を持つ人が仕事を長く続けていくためには、「今できること」を積み重ねるだけでなく、将来的に少しずつでもステップアップしていける道を意識することが大切です。とはいえ、「スキルを高めるってどうすればいいの?」「目指す方向がわからない…」と迷う方も多いはず。
ここでは、テレワークを活用しながら、障がい者雇用の枠組みの中でステップアップを目指すための具体的な方法を紹介していきます。
小さな目標を積み重ねる
ステップアップというと、いきなり「資格取得」や「昇進」などをイメージしてしまうかもしれません。でも、まずは小さな目標を達成することがとても重要です。
たとえば:
1日3時間集中して仕事をする
作業効率を上げる工夫を見つける
1週間に1つ、新しいツールや操作を覚える
こうした目標を立てて、少しずつ達成していくことで、自信にもつながります。発達障害がある場合、「できた!」という実感が積み重なることで、モチベーションが安定するケースが多くあります。
テレワークで働く環境は、「周囲と比較されにくい」「自分のペースで進められる」などの利点があるので、安心して小さなチャレンジができる土台が整っています。
スキルアップのために使えるサービスや制度
「障がい者 テレワーク 求人」といった言葉で求人情報を探すと、最近は就労支援機関が運営するテレワーク型のお仕事が増えているのがわかります。こうした求人の多くでは、スキルアップを支援する仕組みも整っています。
たとえば:
就労移行支援事業所では、仕事に必要なスキルやIT操作の練習をテレワーク形式で行うことができます。
オンラインの学習サイト(例:schoo、ドットインストール、YouTubeなど)を活用することで、自分のペースで学べます。
自治体やハローワークの障がい者職業訓練では、無料または低価格で講座を受けられる制度もあります。
最初は簡単なPC操作やデータ入力、ライティングなど、在宅でできる軽作業からスタートし、少しずつ新しい技術を覚えていく流れが自然です。無理に焦らず、「楽しめる範囲で」進めていくのがポイントです。
信頼を積み重ねて、仕事の幅を広げよう
テレワークという働き方では、対面のやりとりが少ない分、「信頼関係」を築くことが特に重要になります。
例えば:
期日を守る
報連相(報告・連絡・相談)をまめに行う
自分の体調や作業状況を率直に伝える
これらの基本を続けるだけで、企業側からの評価が高まり、より重要な業務を任せてもらえるチャンスが増えます。
また、在宅でできる仕事の中には、キャリアアップにつながるポジションも存在します。
初めはデータ入力からスタートし、のちに品質チェックを任される
ライターとして活動し、後に編集やディレクションも担当する
サポート業務から始めて、チームリーダーへと成長する
このように、障がい者テレワークの環境でも「ただ作業をこなす」だけでなく、「責任ある役割」にステップアップする道は開かれています。
自分らしいステップアップでいい
発達障害を持っていると、「周囲と比べて自分の成長が遅いのでは」と焦ることがあるかもしれません。でも、他の誰かと同じスピードで成長する必要はありません。
あなたが「少しだけ得意になったこと」
あなたが「少しだけ楽になった働き方」
あなたが「昨日よりも不安が減ったこと」
それが、あなたにとっての立派な「ステップアップ」です。
テレワークのように柔軟な働き方ができる時代だからこそ、自分の特性に合った方法で、じっくりスキルを育てていくことができます。
障がい者雇用の中でテレワークを活用する働き方は、発達障害のある人が自分のペースで成長し、キャリアを積み重ねていくための有効な選択肢です。
「ステップアップ」とは、ただ難しいことに挑戦することではありません。 自分らしいスタイルで、一歩ずつ進んでいくこと。それが、長く、安定して働くカギになります。
働きやすくなるための「配慮事項」の伝え方
発達障害のある方が安心して働くためには、自分にとって必要な「配慮」を職場にきちんと伝えることが大切です。
特に、テレワークという環境では、直接顔を合わせる機会が少ないため、伝え方に工夫が必要になります。
ここでは、障がい者がテレワークの現場で役立つ、配慮事項の伝え方と、そのポイントを解説していきます。
「配慮事項」は、わがままじゃない
まず初めに伝えたいのは、「配慮を求めること=甘え」ではない、ということです。
発達障害のある人が快適に働くためには、音や光、コミュニケーション方法、スケジュール管理などに関する配慮が必要になることがあります。こうした配慮がないままだと、ストレスやミスが増え、せっかく得意な仕事も続けにくくなってしまいます。
だからこそ、自分が働きやすい環境を整えるために、事前に必要なことを伝えておくのは、むしろ前向きな「仕事への準備」なんです。
テレワークで伝えるときのポイント
「障がい者 テレワーク」の求人では、オンラインでのやり取りがメインになります。だからこそ、配慮事項の伝え方にも“ひと工夫”が求められます。
具体的には、以下のような形で伝えるとスムーズです。
1. 具体的に伝える
→ 例:「メモを取りながら聞くのが難しいため、会議後にチャットで内容を送っていただけると助かります」
2. 理由をシンプルに説明する
→ 例:「聴覚過敏があるため、ヘッドセットの音量を調整しやすい環境が必要です」
3. できること・できないことをセットで伝える
→ 例:「電話対応は難しいのですが、チャットやメールでの連絡は問題なく対応できます」
このように、自分にとって「何が困るのか」だけでなく、「どうすれば対応できるか」までセットで伝えることで、企業側も対処しやすくなります。
配慮事項は、いつ伝えればいい?
タイミングもとても大事です。
障がい者でテレワーク求人に応募したあと、いつどの段階で伝えるべきか悩む人は多いですが、以下の2つの場面で伝えるのが理想的です。
① 面接や選考の段階で伝える
→ あらかじめ伝えることで、企業も業務やサポート体制を準備できます。
② 採用後、配属が決まった段階で具体的に伝える
→ 実際の仕事に入る前に、より実務に即した配慮内容を伝えることができます。
無理にすべてを最初からオープンにする必要はありませんが、「これだけは最初に伝えないと困る」ということは、遠慮せず話しておくことが大切です。
サポートしてくれる人に相談するのも手
配慮事項を自分でうまく言語化するのが難しい場合は、就労移行支援事業所や障がい者雇用に理解のあるキャリアアドバイザーに相談するのも有効です。
たとえば:
自分では気づけない働きづらさを整理してくれる
面接時の説明を一緒に考えてくれる
書面でまとめて企業に提出する方法をアドバイスしてくれる
このようなサポートを受けることで、自分だけで抱え込まず、安心して配慮を求める環境を作ることができます。
配慮を求めることで、より良い働き方に
実際に配慮事項を伝えたことで、「働きやすくなった」「人間関係のストレスが減った」という声はたくさんあります。たとえば:
ミーティングの参加が不安だったが、議事録の共有で助かった
納期にゆとりを持たせてもらい、安心して作業できた
決まった時間に連絡があるようになり、不安が減った
このように、配慮があることで、自分の力を発揮しやすくなるのです。
そしてそれは、あなたにとっての「働きやすさ」だけでなく、企業にとっても「より良い成果」につながる大切なポイントでもあります。
伝えることで、あなたの強みが活きる
障がい者のテレワークの働き方は、発達障害のある人が自分らしく働くためのチャンスに満ちています。
そのチャンスを活かすためには、自分がどうすれば力を発揮しやすいかを伝えることがカギ。
配慮を求めるのは、自分のためだけではなく、より良い仕事をするための「選択」です。
自分の特性を正しく理解し、必要なサポートを受けながら、自信を持って前に進んでいきましょう。
自己理解が道を開いた。発達障害の当事者が見つけた“自分らしい働き方”
発達障害のある人が「自分に合った働き方」を見つけるために、最も大切なのは自己理解です。
ここでは、ある一人の当事者のエピソードをもとに、「テレワーク」という選択がどのように彼のキャリアと生き方を変えたのかをご紹介します。
田中さんのケース:こだわりが“強み”に変わった瞬間
30代前半の田中さんは、ASD(自閉スペクトラム症)の診断を20代後半で受けました。
正社員として働いていたころは、職場での雑談や急な業務変更が苦手で、何度も転職を繰り返していたそうです。
「まわりに合わせなきゃと思うほど疲れて、自分がダメな人間に感じていた」と、当時を振り返ります。
転機となったのは、就労移行支援事業所でのカウンセリングでした。
支援員から「あなたの“こだわりの強さ”は、正確性や集中力として仕事に活かせる」と言われたのがきっかけで、自己理解が深まっていったといいます。
テレワークに向いていると気づいた瞬間
支援を受けながら、自分の得意・不得意を整理していった田中さん。
その中で、「人との距離感が保てる環境の方が集中できる」「静かな空間で、自分のペースで働ける仕事がしたい」と感じるようになりました。
そして、支援員の勧めで応募したのが「障がい者 テレワーク 求人」で募集していた、データチェックの業務。
「最初はパートからのスタートでしたが、チェックリストに基づいてミスを見つける仕事が自分に合っていて、苦にならなかった」と話します。
自己理解が仕事の質を変えた
田中さんは、在宅勤務で働くようになってから、次第に自分の強みに自信が持てるようになりました。
日々のルーティンが安定し、集中しやすい時間帯に作業を進めることで、成果も上がっていったのです。
企業とのやり取りもチャット中心で、直接的なコミュニケーションが苦手だった田中さんにとっては大きな安心材料になったといいます。
さらに、自分に必要な配慮(例:作業手順をマニュアルで提示してもらう、突発的なタスクの事前予告など)をしっかり伝えるようになってからは、ストレスも減少。
結果的に、半年後には業務のリーダー的ポジションを任されるようになりました。
自分を知ることが、「働く」を変えた
田中さんは今、同じように悩む発達障害のある人に向けて、こんな言葉を贈ってくれました。
「できないことを隠すのではなく、できることを磨いていく働き方もある。テレワークは、自分を否定せずに働ける場だった」
「“自分には無理かも”とあきらめていた頃と比べると、今は働くことが楽しいと感じられます」
このストーリーが伝えてくれるのは、「自己理解の深まり」が自信につながり、自信が「自分に合った働き方」を引き寄せるということ。
「障がい者 テレワーク 求人」は、そのためのきっかけのひとつになり得ます。
あなたにもきっとある、自分だけの“働きやすさ”
今回ご紹介した田中さんのように、働きにくさを感じていた人が「自分らしい働き方」を見つけられるのは、決して特別なことではありません。
大切なのは、「自分にとって働きやすいとは何か?」を見つけていくこと。
そしてそのプロセスに、テレワークという選択肢があることを、ぜひ覚えておいてください。
自分らしいキャリアの描き方──発達障害があっても「働く」は選べる
発達障害があると、働くうえでさまざまな壁にぶつかることがあります。
「空気が読めないと思われたらどうしよう」「何度も注意されるのが怖い」「仕事がうまく続かない」──そんな不安や経験を抱えている方も、少なくないでしょう。
でも、発達障害があるからといって、「働くこと」をあきらめる必要はまったくありません。
むしろ、自分の特性を理解していくことで、あなたにとって働きやすいスタイルや仕事は必ず見つかります。
「こうあるべき」から自由になる
多くの人が、「会社員としてフルタイムで通勤する働き方が正解」と思い込んでしまいます。
けれど、現代の働き方はそれだけではありません。
・週2〜3日から働ける柔軟な求人
・短時間のパートや時給制の業務委託
・スキルを活かしたフリーランスという道
・テレワークによる在宅での安定した仕事
どの働き方も、「正解」かどうかは、あなた自身が決めていいのです。
自分の心や体が疲れすぎず、安心して続けられること。
自分の得意を活かして、価値を発揮できること。
この2つがそろえば、それはもう立派な「キャリア」です。
自分だけの「軸」を持つことがキャリアのスタートライン
キャリアという言葉には、「出世」や「昇進」のイメージがつきがちですが、
本来のキャリアとは、「自分の人生における仕事の選び方・積み重ね方」を意味します。
たとえば、
・「集中しやすい静かな環境で働きたい」
・「人と関わりすぎない仕事がしたい」
・「ひとつの作業に没頭することが得意」
このような“自分の軸”を理解することが、キャリア設計の第一歩になります。
発達障害を持つ方にとって、自己理解が深まるほど、ミスマッチも減り、長く安定して働くことが可能になります。
障がい者のテレワークは、未来の選択肢を広げる扉
このコラムで繰り返し伝えてきた働き方は、制限ではなく可能性を広げる手段です。
・人との距離感をコントロールできる
・自分のペースで働ける
・疲れやすさに配慮しやすい
・苦手な刺激を避けられる
こうしたメリットは、発達障害のある人にとって大きな安心材料になります。
今は、在宅勤務を前提とした求人も増えており、企業側も配慮や合理的な対応に理解のあるところが増えてきました。
最初の一歩は小さくても、そこから始まる未来はきっと大きく広がっていきます。
最後に──「働く」は、あなたのもの
働き方は、誰かのために合わせるものではなく、あなた自身が決めるものです。
「自分らしい働き方を見つけたい」
「無理のないペースで続けられる仕事がしたい」
「得意を活かして誰かの役に立ちたい」
そう思う気持ちがあるなら、きっとあなたにもできる働き方が見つかります。
迷ったとき、立ち止まりたくなったときには、今日読んだ内容をもう一度思い出してください。
そして、あなたの「働く」という選択が、少しずつでも前に進んでいけるよう、心から応援しています。
スタッフコラムのおすすめ記事
-
2025/12/10
大人の発達障害(神経発達症)の理解と効果的な対策
-
2025/05/20
障がい者雇用の魅力的な職種とは?求人の種類とおすすめのお仕事
-
2025/05/20
障がいがあっても大丈夫。自分らしい働き方を家族と一緒に見つけよう
-
2025/05/20
どんな人でも自己分析は内定への近道