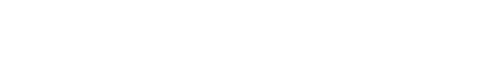2025/05/20
どんな人でも自己分析は内定への近道

スタッフ
こんにちは!障がい者のための在宅就労求人.comです。
今日は内定への近道についてお話していきます。
目次
- 障害があっても「自分らしい仕事」は見つかる
- 自己分析がなぜ大切?障がい者雇用における“内定への鍵”
- 自己理解のステップ①:得意・不得意を言語化しよう
- 自己理解のステップ②:価値観や働き方の希望を整理する
- 自己理解のステップ③:障がい特性と配慮事項を整理しよう
- 自己分析を活かした求人の選び方──“自分らしく働く場所”を見つけるには
- 自己分析が、あなたの“働く力”を引き出す──自分らしいキャリアのはじまり
障害があっても「自分らしい仕事」は見つかる
「障がいがあるから働くのは難しい」「自分にできる仕事なんてあるのかな」──そんな不安を抱えている方や、そのご家族も多いのではないでしょうか。特に就職活動のスタート地点である“自己分析”に対して、「どう進めていいかわからない」「そもそも何を分析するの?」と戸惑う声もよく聞かれます。
ですが、実は自己分析こそが障害者雇用での就職成功のカギになります。自分の得意なことや苦手なことを整理し、希望する働き方や配慮事項を明確にしておくことは、求人探しや面接時の大きな強みになります。これは在宅ワークなど多様な働き方を選べる時代になった今だからこそ、ますます重要になってきているのです。
「障がい者である自分に合った仕事って?」「求人はどう探せばいいの?」「在宅ワークも可能?」といった疑問に対して、まずは自己分析をどう進めるかを軸に、具体的なステップや考え方をご紹介します。
ご家族のサポートの方法も含め、内定までの道のりをわかりやすくお伝えしていきます。
障害があっても、自分らしい働き方はきっと見つかります。その第一歩は、「自分を知ること」から。さあ、一緒に始めてみましょう。
自己分析がなぜ大切?障がい者雇用における“内定への鍵”
就職活動を始めると、求人を探したり、履歴書を書いたり、面接の練習をしたりと、やることがたくさんありますよね。でも、どんなに丁寧に準備しても、「自分がどんな人間なのか」「どんな働き方を望んでいるのか」がわかっていなければ、本当に合った仕事を見つけることは難しくなってしまいます。
そこで大切なのが、自己分析です。
自己分析とは、文字通り「自分を分析する」こと。自分の得意・不得意、好きなこと・苦手なこと、働きたい環境、障害の特性や必要な配慮などを整理していく作業です。この過程は、履歴書の自己PR欄を書くときや、面接で質問に答えるときに、とても役立ちます。
特に障害者雇用枠での就職活動では、自己分析が内定への大きなカギになります。企業側も「どんな配慮をすれば働きやすくなるか」「どんな業務が向いているのか」といった情報を知りたがっています。だからこそ、自分自身がまずそれを理解し、整理しておくことが大切なのです。
また、近年では在宅ワークやテレワークといった柔軟な働き方の求人も増えてきました。しかし、これらの求人に応募する場合でも、自分にとって何が働きやすいか、どんなスケジュールや環境が合っているのかを明確にしておく必要があります。たとえば「朝は体調が安定しないので午後からの勤務を希望したい」「静かな環境で集中できる」など、自己理解がそのまま働きやすさにつながるのです。
さらに、自己分析は“自信”にもつながります。自分をよく知ることで、「自分にもできることがある」と実感できたり、「この仕事なら頑張れそう」と前向きな気持ちになれたりすることも少なくありません。これは精神的な安定や安心感にもなり、結果的に面接でも自然な笑顔が出やすくなったりします。
つまり、自己分析は「内定を勝ち取るための準備」ではなく、「自分らしく働く未来を切り開く第一歩」なんです。
自己理解のステップ①:得意・不得意を言語化しよう
「自分の得意なことってなんだろう?」「苦手なことって言語化しにくい…」
──自己分析を始めようと思ったとき、多くの人が最初につまずくのがこの「得意・不得意の棚卸し」です。特に、障がいのある方は「できないこと」に意識が向いてしまいがち。でも実は、「他の人にはできないけど、自分には自然にできてしまうこと」や、「これをやっているときは時間を忘れてしまう」と感じることの中に、“得意”はちゃんとあるんです。
◆ 他人に負けない、自分だけの「強み」を見つけよう
たとえば以下のようなこと、あなたにも思い当たるものはありませんか?
単純作業を繰り返すのが苦にならず、集中力が持続する
人に優しく接することができ、相手の話を丁寧に聞ける
ルールをしっかり守れる、報告・連絡・相談がきちんとできる
細かいデータや数字をチェックするのが得意
決まった手順を覚えるのが早く、ミスが少ない
自分の体調や心の変化に敏感で、無理をしない自己管理ができる
こうしたスキルや特性は、実際の職場で非常に重宝されます。
たとえば、データ入力や事務補助のような求人では、「正確性」「継続力」「慎重さ」**が求められることが多いため、「ミスが少ない」「集中して取り組める」という特性は大きな強みになります。
また、「人の話をきちんと聞ける」**という特性は、在宅でのカスタマーサポート業務や、チームでのやりとりが必要な仕事でも活かされます。発達障害のある方の中には、ルールに忠実で誠実な対応が得意な方も多く、企業側からも高く評価される傾向があります。
◆ 「やりがい」を感じる瞬間に目を向けてみよう
強みを知るには、「自分がどんなときにやりがいを感じるか」を振り返るのもとても効果的です。
たとえばこんな質問を自分に投げかけてみましょう:
誰かの役に立てたとき、嬉しかったことは?
作業や活動をしていて、「楽しい」「もっとやりたい」と思ったのはどんなとき?
他人から「それ得意だね」「ありがとう」と言われたことは?
【例1】
「学校や作業所で書類を整理する作業が好き。終わったときに『すごく助かりました!』って言われて、もっと頑張ろうと思えた」
→ “整理整頓力” や “人を支える喜び” が自分の原動力かもしれません。
【例2】
「静かな環境で一人でもくもくと作業を進めると集中できる」
→ “集中力” や “一人作業の適性” が強みとして活かせます。
【例3】
「人にありがとうって言われると、もっと頑張りたくなる」
→ “対人支援へのやりがい” を感じている可能性があります。
◆ 苦手なことも、実は「自己理解」のヒント
一方で、自分の「苦手なこと」も無視せずにリストアップしましょう。
朝が弱く、午前中の集中が難しい
複数の指示が同時にあると混乱しやすい
人前で話すのが苦手
騒がしい場所や急な変化にストレスを感じる
こうした苦手の把握は、職場に配慮を求めるときの大切な材料になります。「午前中の勤務時間を午後にしてもらう」「業務をマニュアル化してもらう」など、就労先に伝えるための“交渉材料”にもなるのです。
得意・不得意を言語化するのは、一朝一夕にはできません。でも、少しずつでも構いません。メモ帳やノートに書き出したり、信頼できる家族や支援者と一緒に話し合ったりしながら、「これは自分の強みだ」と思えることを増やしていきましょう。
次の章では、さらに深く踏み込んで「自分はどんな働き方が合っているのか」「何に価値を感じるのか」を整理していくステップに進んでいきます。
自己理解のステップ②:価値観や働き方の希望を整理する
得意・不得意を整理したら、次は「自分に合った働き方ってどんなだろう?」を考えるステップです。就職活動というと「仕事のスキル」が注目されがちですが、実はどう働きたいかという価値観も、仕事選びにおいてとても重要です。
◆ あなたにとって「働きやすい環境」とは?
ここでは、以下のような項目を整理してみると、自分に合った働き方のイメージが少しずつ見えてきます。
1日の中で、体調が安定している時間帯は?
人と話す仕事と、一人で集中する仕事、どちらが向いてる?
毎日決まったスケジュールが落ち着く?それとも柔軟な方がいい?
通勤は苦にならない?それとも自宅の方が安心?
音や光に敏感?にぎやかな職場は苦手?
こうした“自分にとっての働きやすさ”を考えていくと、「在宅ワーク」という選択肢が向いている人も多いことに気づきます。
◆ 在宅ワークという選択肢──自分らしく働くチャンス
近年では、障害者雇用の中でも在宅ワークの求人が増えてきました。在宅なら、通勤の負担がなく、体調に合わせて働く時間を調整しやすいのが特徴です。ここで、実際に多く見られる在宅ワークの職種をいくつかご紹介します。
・ データ入力・事務サポート系
エクセルや専用システムに、数字や文字を入力する業務
書類のスキャンや、PDFからのテキスト抽出など、電話応対なしでできる職種も多く、静かな環境が向いている方におすすめ
・ カスタマーサポート(チャット・メール対応)
メールやチャットでのお問い合わせ対応
決まったテンプレートを使うことも多く、コミュニケーションが苦手な方でも挑戦しやすい、一部では音声対応(電話)もあるが、配慮の相談が可能なケースも
・ クリエイティブ・デザイン系
イラスト、デザイン、動画編集、ライティングなど
スキルが必要になるが、自分のペースで取り組める仕事が多い、発達障害の方など、集中力の高さやこだわりの強さが活かせることも
・ アンケートモニター・文字起こしなどの軽作業
スキマ時間で行える作業型の仕事もあり、「フルタイムでは難しいけど少し働きたい」という方に向いている、特別なスキルがいらず、初心者向けの求人もある
在宅ワークのメリットは、「自分の体調や特性に合わせて働ける」ことにあります。たとえば、午前中は体が重くて動けないけど午後からなら集中できる人、外出に不安がある人、聴覚過敏などの感覚特性がある人──そんな方にとって、在宅勤務は非常に働きやすい環境です。
◆ 自分にとっての「やりがい」も一緒に考えてみよう
在宅ワークでも、オフィス勤務でも、「この仕事をやっててよかった」と思える瞬間があれば、それがやりがいになります。
人から「ありがとう」と言われたとき
できなかったことが少しずつできるようになったとき
コツコツ取り組んだ作業が誰かの役に立っていたと知ったとき
好きなことや得意なことが、仕事に活かせたとき
こうした「嬉しかったこと」や「満足感があったこと」を振り返ってみると、自分が何に価値を感じるか=仕事の満足度につながる軸が見えてきます。
「自分らしい働き方」は、誰かに決められるものではなく、自分で見つけていくものです。そのために、どんな環境が合うのか、どんな仕事なら長く続けられそうか、どんなことにやりがいを感じるか──ひとつずつ、書き出して整理していきましょう。
次の章では、いよいよ自己理解の最後のパート。「障害特性」と「必要な配慮事項」について、実際の求人応募や職場選びにどう活かせるかを掘り下げていきます。
自己理解のステップ③:障がい特性と配慮事項を整理しよう
自己分析の最終ステップは、「自分の障がい特性」と「必要な配慮」についての理解と整理です。
これは就職活動の書類や面接で伝えるためだけではなく、自分自身が働きやすく、安心して過ごすための土台をつくる、とても大切なプロセスです。
◆ 「障がい特性の整理=自分を知ること」
障がい特性の整理というと、つい「何ができないか」ばかりに目が向きがちです。
でも大事なのは、どんな環境やサポートがあれば、自分が本来の力を発揮できるのかを知ること。
たとえばこんなふうに、項目ごとに分けて書き出してみるのがおすすめです
項目ー自分の状態・特徴ー望ましい配慮例
体調ー長時間座ると疲れやすいー定期的な休憩時間の確保
感覚 ー大きな音に敏感ー静かな作業スペース/在宅勤務
コミュニケーションー一度に複数の指示があると混乱するーメールやチャットでの指示が中心/マニュアル化
スケジュール管理ースケジュール通りに動くのが得意ー日報・週間計画のフォーマットがあると安心
これを行うことで、「自分がどんな配慮を受けるとパフォーマンスを発揮しやすいか」が見えてきます。
◆ 伝え方のポイント:「弱点」ではなく「必要なサポート」として
企業に配慮を求めるとき、どう伝えるか悩む人も多いと思います。
でも、ここで意識したいのは、「できないこと」よりも「どうすればできるか」をセットで伝えること。
たとえば、
「対面でのやり取りは緊張してしまうことがあるが、チャットやメールでのやりとりであれば問題なく対応できるため、可能であれば文字中心のコミュニケーション方法をご配慮いただけると助かります」
このように、自分の特性を否定せずに「働くために必要な条件」として伝えると、相手も前向きに受け止めてくれやすくなります。
また、障がい特性や配慮事項を伝える際は、「診断名」だけに頼る必要はありません。「困っていること」と「工夫すればできること」を中心に整理しましょう。
◆ 配慮事項が整理できると「職場選びの軸」になる
自己分析で配慮事項を整理できると、自分に合った職場や求人の選び方がぐっと明確になります。
たとえば、以下のような形で活かせます
「マルチタスクが苦手 → 一つひとつの作業に集中できる業務が多い職場を探す」
「音や人の気配に敏感 → 在宅勤務や個室スペースのある職場が合っている」
「スケジュール管理が苦手 → スケジュール共有ツールが整っている企業を選ぶ」
さらに、面接や履歴書で「どうしてその仕事に応募したのか」を話す際にも、「自分の特性に合っていると感じたから」という説得力のある理由になります。
◆ 自己理解が“自分の安心”につながる
就職はゴールではなく、その後も長く安心して働き続けるためのスタート地点です。
そのためにも、自己理解を深めておくことは、何よりも自分を守る力になります。
自己分析を丁寧に行えば、「無理をしてがんばりすぎてしまう」「自分を責めてしまう」ことも減り、
「自分らしく働くためには、こういう環境が大切なんだ」と前向きに考えられるようになります。
自己分析を活かした求人の選び方──“自分らしく働く場所”を見つけるには
自己分析を通して「自分の強み」や「働くうえで大切な条件」が見えてきたら、次のステップは求人探しです。
でも、ただ闇雲に求人情報を眺めていても、どれが「自分に合っている仕事」なのかはわかりにくいですよね。
ここでは、自己分析の結果を活かして、自分にフィットする求人を選ぶためのヒントをご紹介します。
◆ 「向いている仕事」は、自己分析から見えてくる
たとえば、以下のように自己分析の結果を「求人選びの軸」として活用してみましょう。
【自己分析の気づき・求人選びのポイント】
・一人で集中する作業が得意→データ入力、校正、画像チェック、在宅ワーク中心の仕事
・人との会話が好き、明るく接するのが得意→接客、カスタマーサポート、オンライン接客など
・スケジュール通りに動くのが苦手→柔軟な勤務時間がある求人、フレックスタイム制度のある会社
・通勤や人混みがつらい→在宅勤務OKな企業、テレワーク中心の仕事
・求人を見るときに、自分の「得意・苦手」や「必要な配慮」を軸にして探せば、無理なく働ける仕事が見つけやすくなります。
◆ 在宅ワークの求人を探すときのポイント
特に近年は、障がい者向けの在宅ワーク求人が増えてきました。
「移動が負担」「人とのやり取りが少ない方が落ち着く」という人にとっては、非常に働きやすいスタイルです。
以下のような仕事は、在宅ワークでも応募しやすい職種です。
データ入力・チェック業務
文字起こし・音声書き起こし
Webライティング・記事制作
広報・SNS投稿代行
Webデザイン・コーディング
カスタマーサポート(チャット・メール中心)
ただし、「完全在宅」や「週◯日在宅OK」と書かれているかをしっかり確認しましょう。
「在宅可」と書いていても、実際には出社前提の企業もあります。
◆ 「障害者雇用」枠の求人でチェックすべきポイント
障がい者雇用枠の求人には、「配慮あり」で働ける環境が整っている場合が多く、自己分析で明らかになったニーズを満たしやすい傾向があります。
以下の項目を求人票や企業HPでチェックすると安心です。
勤務時間の柔軟さ(時短勤務・週3〜OKなど)
通院配慮や在宅勤務の有無
仕事内容が明確に記載されているか
面接前に障がい特性について相談できる窓口があるか
自社での障がい者雇用の実績・人数・定着率
また、「障がい者枠の求人専門のサイト」や「就労支援サービス(A型・B型・就労移行支援)」などを活用することで、自分に合った求人を見つけやすくなります。
◆ 求人探しに疲れたら、もう一度「自己分析」に立ち返ってみる
就職活動をしていると、求人を見すぎて「何が自分に向いているのか、またわからなくなってきた…」ということもあります。
そんなときは、もう一度自己分析に戻ってみることが大事です。
自分が心地よく感じる働き方はどんなものか?
今の気持ちや希望はどう変わったか?
本当にやりたい仕事はなんだったか?
自分と向き合いながら求人を見ることで、「この仕事、やってみたい」と思える出会いがきっと増えていきます。
◆ 自分の人生に合う働き方を選ぶ
「自己分析×求人選び」は、自分の未来の暮らしや働き方を決める大切な作業です。
周りと比べる必要はありません。大切なのは、自分が「ここなら働けるかも」「この仕事、ちょっと楽しそうかも」と思えるかどうか。
あなたの経験や強み、希望を活かせる仕事は、必ずあります。
焦らず、自分のペースで、一歩ずつ探していきましょう。
自己分析が、あなたの“働く力”を引き出す──自分らしいキャリアのはじまり
ここまで読んでくださって、ありがとうございます。
このコラムでは「障害があっても、自己分析を通して自分らしい働き方を見つけよう」というテーマでお話をしてきました。
自己分析は、就職活動のためだけのものではありません。
自分の人生を、自分の言葉で語れるようになるためのプロセスです。
それはきっと、障がいや体調などのハードルがあっても「自分らしく働ける社会」に向けた第一歩になります。
◆ 自己分析は、自信の“種”を見つける作業
これまでたくさんの読者さんから「自己PRに書くことがない…」という声を聞いてきました。
でも実際には、誰もがそれぞれの経験・得意・価値観を持っているんです。
毎日体調を見ながら工夫して生活していること
人とのやりとりが苦手でも、コツコツ作業で成果を出してきたこと
家族や支援者との関係を大切にしながら、少しずつ前に進んできたこと
どれも「あなたの力」なんです。
それを言葉にしていく作業が、まさに自己分析。
自信がないと感じる人ほど、自己分析のなかで“自分の強さ”に気づくことができるのです。
◆ 自己分析をしてきたあなたには、もう武器がある
第1章で「自己分析は“自分を知る地図”」という話をしました。
最初は手探りでも、少しずつその地図はできあがってきました。
自分はどんなときにやりがいを感じるか?
苦手なことにはどんな工夫が必要か?
どんな働き方が一番心地よいのか?
その答えを持っているあなたは、すでに「自分の働き方を選ぶ力」を手にしています。
その力をもって、自分に合う求人を選び、企業と対話することができるようになります。
◆ 「自分らしさ」をあきらめない社会へ
障がいがあると、「働けるのかな?」「迷惑をかけてしまわないかな?」と不安になることもあります。
でも、あなたにしかできないことがある。
その力を活かせる職場も、少しずつ増えてきています。
特に在宅ワークや障害者雇用枠の広がりは、「自分に合った働き方が選べる時代」になってきた証です。
そこに向かって、自分のことをちゃんと伝えられることが、一番の強みになります。
◆ 自己分析はゴールではなく「スタート」
このコラムでお伝えしたかったのは、自己分析をしたら終わり、ではないということです。
それは、あなたが「自分の可能性に気づいた」スタートライン。
在宅での仕事に挑戦してみる
支援機関に相談してみる
初めての職務経歴書を書いてみる
家族と「これからの働き方」について話してみる
どんな小さな一歩でも大丈夫です。
あなたが「自分で選び、自分で決める」働き方に向かって歩き出すために、自己分析を活かしてほしいと思います。
◆ 最後に──あなたへ、エールを
自分らしい働き方は、きっとひとつじゃありません。
障がいがあっても、在宅でも、通勤ができなくても、選択肢はたくさんあります。
大切なのは、自分に合う形を、あきらめずに探すこと。
自己分析は、そのための一番の味方です。
あなたが自分らしい働き方を見つけて、笑顔で働ける日が来ることを、心から願っています。
スタッフコラムのおすすめ記事
-
2025/12/10
大人の発達障害(神経発達症)の理解と効果的な対策
-
2025/05/20
障がい者雇用の魅力的な職種とは?求人の種類とおすすめのお仕事
-
2025/05/20
障がいがあっても大丈夫。自分らしい働き方を家族と一緒に見つけよう
-
2025/05/20
どんな人でも自己分析は内定への近道