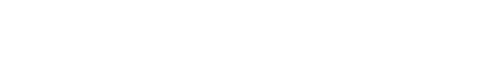2025/05/20
「障害者手帳」を持つとできること|就職・支援・生活の広がる可能性

スタッフ
こんにちは!障がい者のための在宅就労求人.comです。
今日は障害者手帳を持つとできることについてお話していきます。
目次
- はじめに|「障害者手帳」が広げる、生活と働き方の新しい可能性
- 障害者手帳の種類とは?それぞれの特徴と対象を解説
- 障害者手帳の申請方法~手続きの流れと必要書類~
- 障害者手帳を持つデメリットはある?
- 障害者手帳がもたらす生活と仕事への影響
- 障害者手帳で広がった生活と仕事の可能性──実際の体験談から学ぶ
- まとめ
はじめに|「障害者手帳」が広げる、生活と働き方の新しい可能性
障害者手帳──それは、ただの「証明書」ではありません。
制度や支援を受けやすくする“パスポート”であり、あなたの生活や働き方の選択肢を広げる力を持った存在です。
「手帳を取得すると、生活にどんな影響があるの?」「働くうえでどんなサポートが受けられるの?」
そんな疑問を持つ方も多いかもしれません。
なので、障害者手帳の種類や申請方法、取得後に利用できる制度やメリット・デメリットについてわかりやすく解説していきます。
自分らしく安心して暮らし、働くための一歩として、障害者手帳の可能性を一緒に見つめていきましょう。
障害者手帳の種類とは?それぞれの特徴と対象を解説
障害者手帳は、障がいのある方が公的な支援を受けやすくするための重要な証明書です。種類は大きく分けて「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3つに分類されており、それぞれ対象となる障がいの種類や目的が異なります。まずは、これらの手帳がどのような違いを持っているのかを確認してみましょう。
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、視覚・聴覚・肢体不自由など、身体に障がいがある方を対象とした手帳です。障がいの程度に応じて1級から6級までに区分され、数字が小さいほど障がいの程度が重いことを示しています。
この手帳を持つことで、公共交通機関の割引や、自動車税・軽自動車税の減免、住宅改修の助成など、日常生活や移動に関する支援が受けられます。また、就労支援サービスの対象にもなり、障害者雇用枠での応募など、働き方にも良い影響をもたらします。
療育手帳(愛の手帳・みどりの手帳など)
療育手帳は、知的障がいのある方が対象となる手帳です。自治体によって名称は異なり、「愛の手帳」「みどりの手帳」といった独自の呼び方が使われることもあります。知的障がいの程度に応じて「A(重度)」または「B(中・軽度)」に区分されるのが一般的です。
療育手帳を持っていることで、特別支援教育、福祉サービス、医療費助成、バスや電車の割引など、生活全般にわたるサポートを受けることができます。また、就労支援や障害者雇用制度の対象にもなり、働くチャンスを広げる一助となります。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、統合失調症、うつ病、双極性障害(躁うつ病)、発達障害など、精神障がいがある方を対象としています。障がいの程度に応じて1級から3級に区分され、こちらも1級が最も重い障がいとされています。
この手帳を取得することで、医療費の助成、税制優遇、公共料金の割引、通院交通費の支援などが受けられる場合があります。精神障がいは外からは見えにくいため、手帳があることで周囲に自分の状況を理解してもらいやすくなり、就職活動や職場での配慮にもつながります。
障害者手帳の申請方法~手続きの流れと必要書類~
障害者手帳は、障がいがあると診断されたからといって自動的に交付されるわけではなく、申請を通じて交付される制度です。手帳の種類により申請の内容や手続きが異なるため、あらかじめ必要な流れや準備すべき書類を理解しておくことが重要です。今回は、障害者手帳の申請に関する基本的な流れと必要書類を詳しく解説します。
どこで申請するの?
障害者手帳の申請は、お住まいの市区町村の福祉課や障がい福祉窓口などで行うことができます。初めて手帳を申請する際には不安があるかもしれませんので、事前に窓口に電話で問い合わせをしてから訪問するのが安心です。また、市区町村によって名称や担当窓口が異なることがあるため、インターネットで「障害者手帳 〇〇市(住んでいる自治体名)」と検索し、どの窓口で手続きを行うかを確認するとスムーズに進めることができます。
申請の主な流れ
障害者手帳を取得するためには、いくつかのステップを踏む必要があります。以下に、その主な流れを紹介します。
1. 診断書の取得
まず最初に必要なのは、障がいの状態を証明するための診断書です。この診断書は、手帳の種類によって異なる様式が求められます。例えば、身体障害者手帳を申請する場合は、身体障害者福祉法に基づいた診断書が必要です。精神障害者保健福祉手帳を申請する場合は、精神科医が作成した診断書が求められます。知的障害がある場合には、療育手帳のために更生相談所での判定が必要です。
診断書は、障害の種類や等級、必要な支援内容を明確に示す重要な書類であり、手帳の交付に大きな影響を与えるため、信頼できる医師や指定医による診断を受けることが推奨されます。
2. 必要書類をそろえる
診断書を取得したら、次に申請に必要な書類を集めます。一般的に必要となる書類は以下の通りです:
診断書または判定書:障がいの状態を証明する書類。
申請書:自治体の窓口で配布されるか、自治体のホームページからダウンロードできます。
写真:縦4cm×横3cmのサイズで、最近6ヶ月以内に撮影されたもの。
本人確認書類:マイナンバーカードや健康保険証など、本人であることを確認できる書類。
これらの書類を揃えたら、窓口での申請準備が整います。
3. 窓口で申請を行う
必要書類をすべて準備したら、住民票がある市区町村の福祉課や障がい福祉窓口で申請を行います。申請書類を提出し、内容に不備がなければ、審査が開始されます。審査には数週間から1ヶ月程度かかることがありますが、場合によっては、医師への追加の照会や、障害の状態の確認が行われることもあります。
4. 手帳の交付
審査が完了し、交付が決定すると、市区町村から交付の通知が届きます。交付には通常、数週間から1ヶ月程度が必要です。手帳は原則として本人が受け取りに行くことが求められますが、代理人による受け取りが認められている場合もあるので、事前に確認しておくと安心です。
ポイント:医師選びは慎重に
診断書は障害の等級や支援内容に直結する重要な書類です。そのため、診断書を作成する医師は慎重に選ぶ必要があります。特に精神障害者保健福祉手帳や身体障害者手帳の申請の場合、指定医による診断が必要となることが多いため、事前に医療機関に「指定医」の有無を確認し、診断を受けることをお勧めします。適切な医師の診断を受けることで、障害者手帳の申請がスムーズに進むとともに、手帳の交付後の支援も円滑に受けられるようになります。
障害者手帳の申請にあたっての注意点
障害者手帳の申請は難しい手続きではありませんが、診断書の取得や書類の準備に時間がかかることがあります。また、申請内容に不備がないか慎重に確認することも重要です。不安がある場合は、自治体の福祉相談窓口や、就労移行支援事業所、専門の相談員に相談してみるのも一つの方法です。専門家からのアドバイスを受けることで、手続きがスムーズに進むだけでなく、障害者手帳をどのように活用すべきかについても適切な助言を得ることができます。
障害者手帳の取得は、支援を受けるための第一歩です。手帳を持つことで、障がいに関連するさまざまなサービスや支援を受けやすくなり、生活や仕事の質を向上させることができます。申請にあたっては無理をせず、確実に準備を進めていくことが大切です。
障害者手帳を持つデメリットはある?
障害者手帳を取得することで、さまざまな支援や優遇措置を受けられる反面、「デメリットがあるのでは?」と不安に思う方も少なくありません。ここでは、障害者手帳を持つことによって考えられる注意点や、誤解されがちな点について詳しく解説していきます。
デメリットと感じるかは、状況によって変わる
まず前提としてお伝えしたいのは、「障害者手帳を持つ=必ずデメリットがある」ということではありません。むしろ、手帳を持つことで受けられる支援や配慮は、生活や働き方の選択肢を広げてくれるものです。
とはいえ、一部の人にとってはデメリットと感じられる可能性のある点もあります。そうした例をいくつか見ていきましょう。
1. 周囲に障害が知られることへの不安
障害者手帳を提示する場面では、相手に自分の障害が知られる可能性があります。これは、就職活動や職場での配慮を求める際に避けて通れないこともあり、「知られたくない」「偏見を持たれるのでは」といった不安に繋がることがあります。
ただし、実際には「障害者手帳を持っている=能力がない」といった誤解をしている企業は少なくなってきています。むしろ、手帳を提示することで必要な配慮を正しく受けられる可能性が高まります。
2. 就職時に選べる雇用枠が変わる
障害者手帳を持っていると、「障害者雇用枠」での応募が可能になります。これは、手帳を持っていることでむしろ就職のチャンスが広がるという側面もありますが、「一般雇用枠で応募できないのでは」と誤解されることもあります。
実際には、障害者手帳を持っていても一般枠に応募することは可能です。また、障害者雇用枠の方が配慮やサポートを受けやすく、自分らしく働きやすいと感じる方も多くいます。
3. 自己申告や申請の手間がある
障害者手帳を利用して各種サービスや支援を受けるには、手帳の提示や申請手続きが必要になります。「毎回書類が面倒」「対応していない窓口もあった」と感じるケースもあるかもしれません。
とはいえ、近年は多くの施設や企業が障害者手帳に対応しており、申請もオンライン化されてきているなど、利便性は向上しています。
4. 精神障害者保健福祉手帳への誤解
特に精神障害者保健福祉手帳については、周囲の理解がまだ十分とはいえず、誤解を受ける場面もあります。例えば「精神障害=危険」などという偏見を持つ人も一部に存在します。
しかし、こうした誤解をなくすためにも、正しい情報発信と理解促進が社会全体で進められています。また、手帳の提示はあくまで任意であり、必要な場面でだけ提示すればよいので、プライバシーが損なわれることはありません。
デメリットをどう捉えるかは、自分次第
障害者手帳を持つことによる「デメリット」は、あくまで感じ方の違いによるものであり、それが一概に悪いこととは限りません。実際、多くの方が手帳を活用しながら、自分らしく生活し、働く道を切り開いています。
大切なのは、「手帳を持つこと=選択肢が広がること」だと捉えることです。就職の場面では、手帳があることで受けられるサポートや合理的配慮が充実しており、むしろ安心して働ける職場に出会える可能性も高まります。
障害者手帳がもたらす生活と仕事への影響
障害者手帳を取得することで、私たちの生活や働き方にはどのような変化がもたらされるのでしょうか?この章では、具体的にどんな支援が受けられるのか、そしてそれによってどのように日常やキャリアが前向きに変化するのかを詳しく紹介します。
生活面でのサポートと変化
まず、生活面では、障害者手帳によって受けられる支援や優遇措置が豊富にあります。たとえば、次のような支援が挙げられます。
公共交通機関の割引
多くの自治体では、電車やバスなどの公共交通機関の運賃が割引されます。これにより、通院や外出時の経済的負担が軽くなり、外出のハードルが下がることで生活の自由度が高まります。
医療費の助成
医療費の自己負担が軽減される制度が整っている地域もあります。慢性的な通院や医薬品の購入が必要な方にとっては、金銭的な安心感が大きくなります。
税制上の優遇
所得税・住民税の控除や自動車税の減免、相続税の優遇など、税制面でもさまざまな支援があります。これらの制度を活用することで、家計への負担を大きく減らすことができます。
公共施設の利用割引
博物館や動物園、公営のスポーツ施設などの入場料が割引または無料になるケースも多く、家族や友人とのレジャーの機会をより気軽に楽しめるようになります。
就労面での影響と選択肢の広がり
障害者手帳がもたらす影響は、生活だけでなく「仕事」においても大きな変化をもたらします。
障害者雇用枠での応募が可能に
障害者手帳を持つことで、企業の「障害者雇用枠」での就職が可能になります。これは、障がいのある方の能力や特性を理解し、配慮したうえで働ける環境を提供するために設けられている制度です。
障害者雇用枠では、面接時に配慮してほしいことを伝える機会が設けられたり、入社後の支援体制が整っていたりすることが多いため、自分のペースで安心して働けるという声も多く聞かれます。
在宅勤務など柔軟な働き方の実現
近年では、在宅勤務を積極的に取り入れている企業も増えており、障害者手帳を活用して「自宅で働く」という選択肢を選ぶ方も増加しています。体調や通院スケジュールに合わせて働けることで、働き続けやすい環境が整ってきています。
ハローワークや支援機関の活用
障害者手帳を持っていると、ハローワークの障害者専門窓口や、就労移行支援などの福祉サービスを受けやすくなります。たとえば、職業相談、応募書類の作成支援、面接練習など、仕事探しにおいて心強いサポートを受けられます。
合理的配慮が得られやすくなる
職場での配慮(合理的配慮)をお願いする際にも、障害者手帳を持っていることで理解が得られやすくなります。例えば、「通院のために定期的な早退が必要」「静かな環境で仕事がしたい」など、個々の事情に合わせた働き方を交渉しやすくなるのです。
自分らしい生活と働き方を手に入れるために
障害者手帳を取得することによって、支援を受けやすくなるという点は、決して「甘え」ではなく、「適切な権利の行使」です。むしろ、自分らしく、長く働き続けるための手段として前向きに捉えるべきものです。
「手帳を取得したからこそ、安心して外出できるようになった」「希望する働き方を実現できた」という方も少なくありません。大切なのは、「制度を活かして、自分らしく生きること」です。
障害者手帳で広がった生活と仕事の可能性──実際の体験談から学ぶ
障害者手帳を持つことで、生活や働き方にどのような変化が起きるのか――。制度の説明だけでは、なかなか具体的にイメージしにくい方も多いかもしれません。そこで、実際に手帳を取得した方々の体験談を紹介し、その影響やメリットを具体的に見ていきましょう。これから紹介する事例を通して、障害者手帳が生活と仕事にどれほど大きな影響を与えるかをご理解いただけると思います。
事例1:手帳取得で復職のハードルが下がった(精神障害者保健福祉手帳/30代・男性)
うつ病で長期間仕事を休んでいたAさん(30代・男性)は、再就職に強い不安を感じていました。「もう一度働ける自信がない」という思いが募り、就職活動に踏み切れずにいました。そんな時、通院していたクリニックの医師から「精神障害者保健福祉手帳を取得してみては?」とアドバイスを受け、手帳を取得することにしました。手帳を取得したことにより、ハローワークでの支援内容が大きく変わりました。障害者雇用枠の求人情報を紹介してもらえるようになり、配慮を受けながら働ける職場を見つけることができました。結果的に、Aさんは段階的な復職を果たし、以前よりも安心して働ける環境を手に入れることができました。
「自分の体調や特性を理解して受け入れてくれる職場に出会えたおかげで、前よりずっと安心して働けるようになりました。最初は手帳を持つことに抵抗がありましたが、今では“必要なサポートを得るための大事なツール”だと感じています。」
事例2:通勤が難しい自分でも、在宅で働ける道が見つかった(身体障害者手帳/40代・女性)
Bさん(40代・女性)は、足の障害により長時間の通勤ができず、働くことを諦めかけていました。しかし、障害者手帳を取得後、障害者向けの求人サービスを利用した結果、在宅勤務の可能性を見出しました。求人サービスでは、在宅勤務可能なライターの仕事を紹介され、パソコンスキルを活かして自宅での勤務がスタートしました。これにより、Bさんは通勤の負担から解放され、自分のペースで仕事を進められるようになりました。
「もし障害者手帳を持っていなければ、在宅勤務の求人を見つけることも、企業と交渉することも難しかったと思います。手帳を取得してから、“障がいがあるからできない”ではなく、“どうやったらできるか”を一緒に考えてくれる環境に出会えたことが、何よりありがたかったです。」
事例3:税金・公共交通機関の割引で生活が少し楽になった(知的障害者/20代・男性・家族の声)
Cさん(20代・男性)は、知的障害を持っている息子さんを育てている母親です。障害者手帳を取得することで、息子さんの日常生活や福祉サービスへのアクセスがスムーズになり、生活が格段に楽になったと語ります。公共交通機関の割引や医療費の助成、さらには税制の優遇措置を受けられるようになり、家計の負担も軽減されました。また、障害者手帳を活用することで、福祉サービスや支援が受けやすくなり、地域での生活も以前より快適になったそうです。
「書類の準備や手続きは少し大変でしたが、受けられる支援が想像以上に多くて、障害者手帳を取得して本当に良かったと思います。子どもの可能性を広げるきっかけにもなりました。手帳を持つことで、親としても自信を持ってサポートできるようになりました。」
障害者手帳は「できること」を広げるサポートツール
これらの事例から分かるように、障害者手帳を取得したことで「働く」「暮らす」という日常生活に大きな変化が生まれています。自分に合った仕事を見つけやすくなった、生活の負担が軽減された、そして必要なサポートが受けやすくなった――それぞれが、手帳を“活用”したからこそ得られた成果です。
もちろん、手帳を持つことに不安を感じる方も少なくありません。しかし、障害者手帳は決して単なる「証明書」ではなく、「自分らしく生きるための選択肢を広げる道具」として捉えることが重要です。制度に頼るだけでなく、自分の生活や働き方をどう進めていくかを考えるための第一歩として、手帳を活用することで、より多くの可能性を手に入れることができます。
障害者手帳は、ただの証明書ではなく、生活の質を向上させるための強力なサポートツールであり、自分らしく生活し働くための「力」を与えてくれる存在だと言えるでしょう。
まとめ
障害者手帳を取得することで、障害を抱えながらも生活の質や仕事の幅を広げることが可能になります。手帳の種類や申請方法、取得にかかる期間など、最初は知らないことが多かったかもしれませんが、このコラムを通じて、障害者手帳を活用する重要性やそのメリットについて理解が深まったのではないでしょうか。
手帳を持つことにより、例えば就労においては障害者雇用枠に応募でき、企業からの配慮を受けることができる場合があります。これは、働く上での大きな助けになります。また、税制優遇や公共交通機関の割引、さらには医療費の助成など、日常生活の負担を軽減する支援を受けられることも手帳の大きなポイントです。さらに、福祉サービスの利用や支援が受けやすくなり、生活全般のサポートが整いやすくなります。
障害者手帳を持つことで、「自分らしく生きる」という視点が広がり、自分の特性を理解した上で、適した仕事の選択肢が増えます。例えば、在宅ワークやフレキシブルな勤務形態など、自分のライフスタイルに合わせた働き方ができる環境が整ってきていることも大きな変化です。
手帳を取得することが目的ではなく、手帳を活用して生活や仕事に役立つサポートを得ることが大切です。自分にとって最適な支援を受けながら、社会で活躍できる場所を見つけるために、積極的に制度を利用しましょう。
障害者手帳は、単なる「証明書」ではなく、自分の特性を理解し、社会との橋渡しをするための重要なツールです。もし、手帳を持つことに不安を感じることがあっても、専門的なサポートを受けながら、前向きに活用していくことができます。
キャリアアドバイザーからのメッセージ
障害者手帳を持つことには大きな意味があります。それは、ただ制度に基づいたサポートを受けるためだけではなく、あなた自身が社会の中でどのように自分らしく働いていくか、生活していくかの選択肢を広げる大切な一歩だからです。
私は日々、多くの障がい者の方々と接していますが、最も大切なのは、自分の強みや特性を理解し、それを活かす方法を見つけることだと感じています。障害者手帳を持つことで、その特性に合わせた働き方や支援が受けられるため、あなたの強みを最大限に活かしたキャリア形成が可能になります。
また、障害者手帳を持っていることで、求人サイトやエージェント、就労支援機関から提供される求人情報やサポートが変わります。障害者雇用枠を利用することで、企業も障害に配慮した勤務環境を整え、あなたがより自分らしく働ける場所を見つける手助けをしてくれるはずです。
最初は手帳を持つことで不安を感じることもあるかもしれませんが、障害者手帳はあなたの可能性を広げるための「扉」となるものです。サポートを受けることで、過去の経験やスキルを活かしながら、障害の有無に関わらず活躍できる場所を見つけられるでしょう。
もし障害者手帳を取得することに迷っている場合や、どのように活用すべきか不安に感じている場合でも、無理に一人で考えずに、キャリアアドバイザーに相談してみてください。専門的な視点でアドバイスを行い、あなたに合った最適な働き方をサポートします。
手帳を活用することで、あなたの生活はさらに充実し、仕事の幅も広がります。自分のペースで無理なく、着実に一歩ずつ前進していきましょう。
スタッフコラムのおすすめ記事
-
2025/12/10
大人の発達障害(神経発達症)の理解と効果的な対策
-
2025/05/20
障がい者雇用の魅力的な職種とは?求人の種類とおすすめのお仕事
-
2025/05/20
障がいがあっても大丈夫。自分らしい働き方を家族と一緒に見つけよう
-
2025/05/20
どんな人でも自己分析は内定への近道